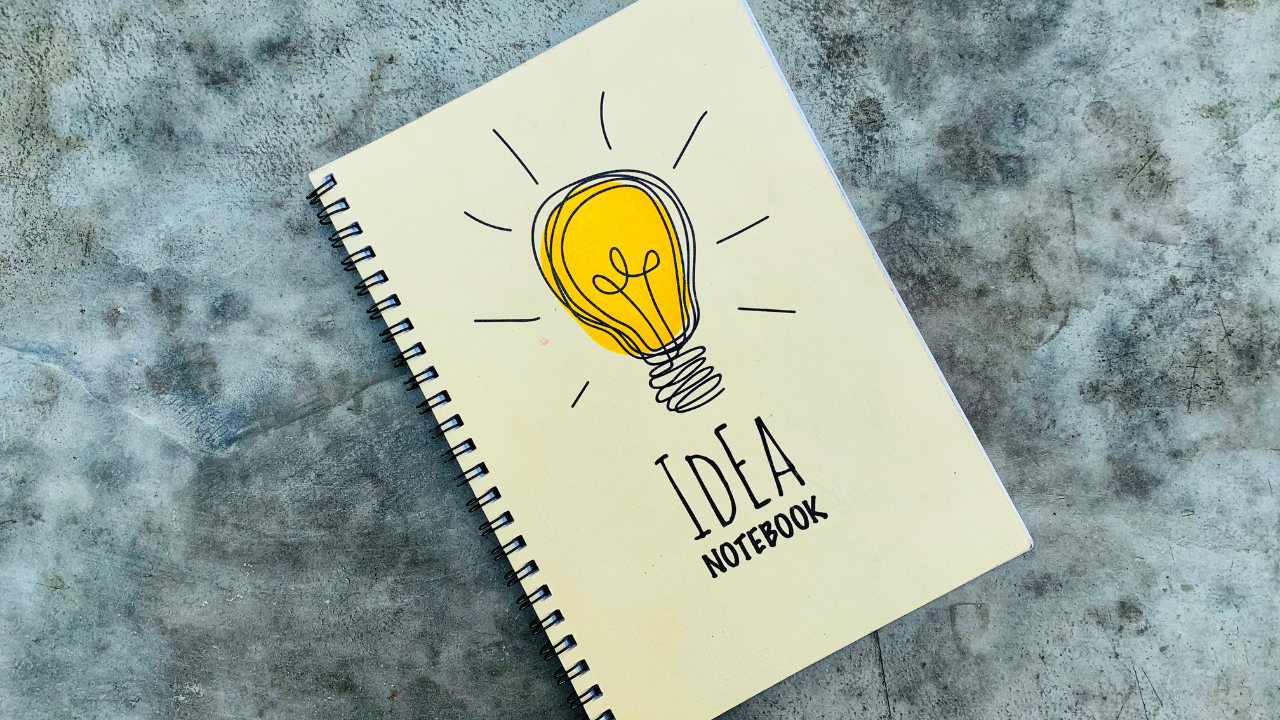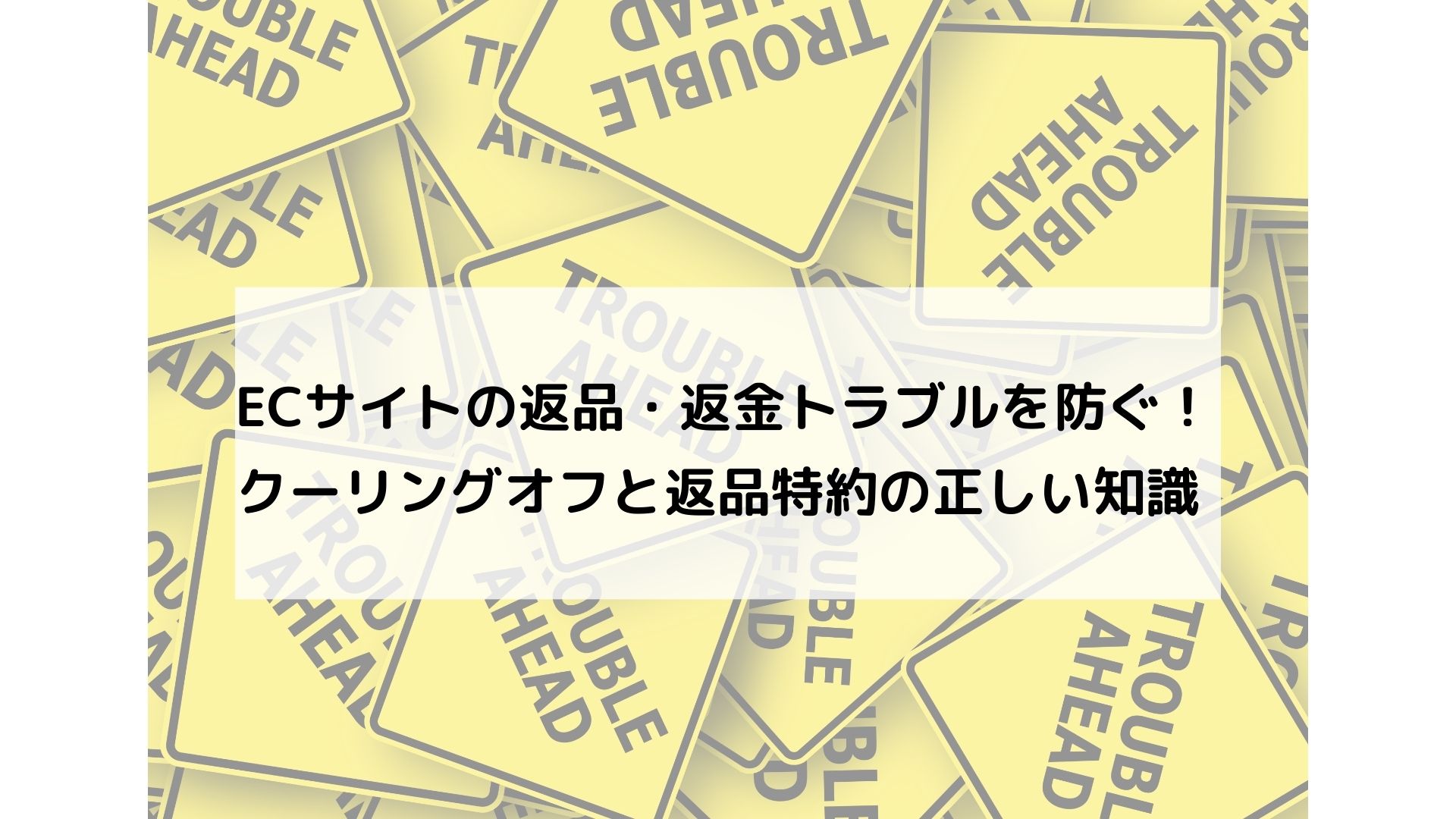ECサイトを通じて自社製品を販売する事業者の皆様にとって、製品の安全性は最重要課題の一つです。
もし、販売した製品が原因で消費者に損害を与えてしまった場合、PL法(製造物責任法)に基づき、損害賠償責任を負う可能性があります。
本記事では、ECサイト運営者が知っておくべきPL法の基礎知識から、具体的な責任範囲、対策、トラブル発生時の対応までを、自社で製造・加工した食品を販売する事業者を例に分かりやすく解説します。
1. PL法(製造物責任法)とは?ECサイト運営者が知っておくべき基本
PL法は、製造物の欠陥によって消費者に生命、身体、財産に損害が生じた場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を請求できる法律です。
ECサイト運営者も、自社で製造・加工した製品を販売する場合、このPL法の適用を受ける可能性があります。
1.1. PL法の目的と背景
PL法は、消費者の安全確保と、製造業者等の責任を明確にすることで、被害者の救済を図ることを目的として1995年に施行されました。
高度経済成長期以降、製品の複雑化や大量生産化が進む中で、製品事故による被害が深刻化し、従来の民法では被害者の救済が十分に行えないケースが増えたことが背景にあります。
1.2. PL法の対象となる「製造物」とは?
PL法の対象となる「製造物」とは、製造または加工された動産を指します。
ECサイトで販売される商品であれば、食品、家電製品、衣料品、家具など、ほとんどのものが該当します。
※ソフトウェアや不動産は対象外となります。
1.3. PL法の対象となる「欠陥」とは?
PL法における「欠陥」とは、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを指します。
具体的には、以下の3つの種類があります。
- 設計上の欠陥: 製造物の設計段階における安全性の問題
- 製造上の欠陥: 製造工程における不良や管理体制の不備による問題
- 指示・警告上の欠陥: 製品の取扱説明書や注意書きの不備による安全性の問題
1.4. ECサイト運営者が「製造業者等」となる場合
PL法における「製造業者等」には、実際に製品を製造・加工した事業者のほか、輸入業者、さらに、自己の氏名、商号、商標などを表示して製造物として販売した事業者も含まれます。
ECサイト運営者が自社ブランドで食品を販売する場合、たとえ製造を外部に委託していたとしても、「自己の氏名等を表示した製造業者」としてPL法の責任を負う可能性があります。
1.5. PL法と民法の違い
従来の民法では、損害賠償請求を行うためには、事業者の故意または過失を被害者が証明する必要がありました。
しかし、PL法では、製造物の欠陥と損害との間の因果関係を被害者が証明すれば、事業者の過失を証明する必要はありません。
これにより、被害者による損害賠償請求が容易になりました。
2. 食品ECサイト運営者が負う可能性のあるPL法上の責任
「自社で製造・加工した食品をECサイトで販売する事業」を営んでいる場合を例に、どのようなケースでPL法上の損害賠償責任を負う可能性があるかを解説します。
2.1. 設計上の欠陥による事故
例)
アレルギー物質の表示漏れ、賞味期限の設定ミス、不衛生な製造ラインの設計などにより、消費者がアレルギー反応を起こしたり、食中毒になったりした場合。
責任)
アレルギー物質の表示は、食品表示法で義務付けられていますが、設計段階での確認不足はPL法上の欠陥とみなされる可能性があります。
賞味期限の設定ミスも、通常有すべき安全性を欠いていると判断される可能性があります。
2.2. 製造上の欠陥による事故
例)
製造工程における異物混入、加熱不足による細菌の繁殖、包装不良による品質劣化などにより、消費者が健康被害を受けた場合。
責任)
製造工程における品質管理体制の不備は、PL法上の欠陥とみなされます。
異物混入や細菌繁殖は、通常有すべき安全性を欠いている明白な例です。
2.3. 指示・警告上の欠陥による事故
例)
アレルギーに関する注意喚起の不足、誤った調理方法の指示、保存方法の記載漏れなどにより、消費者が健康被害を受けた場合。
責任)
食品には、アレルギー物質や調理・保存上の注意点など、消費者が安全に摂取するための情報提供義務があります。
これらの指示・警告が不十分である場合、PL法上の欠陥とみなされる可能性があります。
2.4. 具体的な損害賠償の範囲
PL法に基づき損害賠償が認められた場合、ECサイト運営者は被害者に対して以下の損害を賠償する責任を負います。
- 治療費:事故による怪我や病気の治療にかかった費用
- 入院費:入院にかかった費用
- 慰謝料:精神的な苦痛に対する賠償金
- 逸失利益:事故による休業や後遺症による将来的な収入の減少
- 葬儀費用(死亡の場合):死亡事故の場合の葬儀にかかった費用
- 財産上の損害:食品の廃棄費用や、事故によって使用できなくなった財産の損害
損害賠償の金額は、被害の程度や状況によって大きく変動する可能性がありますが、万が一多数の被害者が発生した場合、事業の継続が困難になるほどのダメージを受ける可能性があります。
3. 食品ECサイト運営者がPL法対策として実施すべきこと
PL法による損害賠償責任を負わないためには、日頃から製品の安全性確保に努めることが重要です。
また食品ECサイト運営を例に、実施すべき具体的な対策について解説します。
3.1. 製品の安全性に関する知識の習得
食品衛生法、食品表示法、PL法など、食品の安全性に関する法令や知識を習得することが基本です。
- 食品衛生法:食品の製造・加工、販売などに関する衛生管理の基準を定めた法律
- 食品表示法:食品の原材料、添加物、アレルギー物質、栄養成分などの表示に関するルールを定めた法律
食品に限らず、これらの法律を遵守することは、PL法上の責任を回避するための第一歩となります。
3.2. 製造・加工工程における品質管理の徹底
HACCP(ハサップ)に基づいた衛生管理システムを導入するなど、製造・加工工程における品質管理を徹底することが重要です。
※HACCP:食品中の危害要因(微生物、化学物質、物理的異物)を特定し、管理するための国際的な衛生管理システム
HACCPを導入し、適切な衛生管理を行うことで、製造上の欠陥による事故リスクを低減できます。
管理システムや業界標準の管理基準などがある場合、それらを遵守して管理体制を構築しましょう。
3.3. アレルギー物質、賞味期限等の表示の徹底
食品表示法に基づき、アレルギー物質、賞味期限、原材料などを正確かつ分かりやすく表示することが重要です。
- アレルギー物質の表示漏れは、消費者の健康被害に直結する重大な欠陥となります。
- 賞味期限の誤表示や記載漏れも、食品の安全性に関わる問題です。
行っている事業や製品に関する法律・規制を理解し、必要な表示に対応しましょう。
3.4. 取扱説明書、注意書き等の充実
食品の適切な調理方法、保存方法、アレルギーに関する注意喚起などを、分かりやすく記載した取扱説明書や注意書きを作成し、製品に同梱またはECサイト上に掲載することが重要です。
- 消費者が安全に食品を摂取できるよう、必要な情報を適切に提供することが、指示・警告上の欠陥を防ぐための対策となります。
- 法律で必要な表示だけではなく、消費者が分かりやすい・誤解のない取扱説明書・注意書きとしましょう。
3.5. PL保険への加入
万が一、製品事故が発生し、損害賠償責任を負うことになった場合に備えて、PL保険(生産物賠償責任保険)に加入することを検討しましょう。
- PL保険に加入していれば、損害賠償金や訴訟費用などを保険金でまかなうことができます。
- 保険の種類や補償範囲は様々なので、自社の事業規模やリスクに合わせて適切な保険を選ぶことが重要です。
- 様々な保険会社からPL保険が提供されているほか、商工会議所による中小企業向けのPL保険などもあります。
参考)ビジネス総合保険制度
|https://www.ishigakiservice.jp/pl
4. 製品事故が発生した場合のECサイト運営者の責任と対応
万が一、販売した食品による製品事故が発生した場合、ECサイト運営者はPL法に基づき損害賠償責任を負う可能性があります。
迅速かつ適切な対応が、被害の拡大を防ぎ、二次的なトラブルを避けるために重要です。
以下では、製品事故が発生した場合にどのような対応が必要か、概要を紹介します。
4.1. 消費者からの連絡受付と初期対応
消費者から製品事故に関する連絡を受けた場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認することが重要です。
- いつ、どこで、どのような状況で事故が発生したのか
- 被害者の症状や損害の程度
- 製品のロット番号や購入時期
これらの情報を丁寧にヒアリングし、記録に残します。
4.2. 原因調査と事実確認
社内で事故の原因調査を行い、事実関係を正確に把握します。必要に応じて、専門機関に調査を依頼することも検討します。
- 製造工程の記録、原材料の検査記録、出荷記録などを確認する
- 同じロットの製品に同様の事例がないか確認する
4.3. 消費者への情報提供と謝罪
調査結果に基づき、消費者に対して事故の原因や状況、今後の対応について誠意をもって説明し、謝罪することが重要です。
- 隠蔽したり、責任を回避するような態度は、消費者の不信感を増幅させ、事態を悪化させる可能性があります。
4.4. 損害賠償に関する協議
PL法に基づき損害賠償責任が認められる場合、消費者との間で損害賠償に関する協議を行います。
- 弁護士などの専門家を交え、適切な賠償金額や支払い方法について話し合うことが望ましいです。
4.5. 関係機関への報告
重大な製品事故が発生した場合は、消費者庁や保健所などの関係機関に速やかに報告する必要があります。
- 報告を怠ると、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。
4.6. 再発防止策の実施
事故の原因を究明し、再発防止策を策定・実施することが最も重要です。
- 製造工程の見直し、品質管理体制の強化、表示内容の改善など、具体的な対策を講じます。
- 再発防止策を公表することで、消費者の信頼回復に努めます。
まとめ
ECサイトで自社製造・加工した製品を販売する事業者は、PL法に基づく損害賠償責任を負う可能性があることを十分に理解しておく必要があります。
日頃から製品の安全性確保に努め、万が一の事故発生時には迅速かつ適切な対応を行うことが、事業の継続と信頼維持のために不可欠です。
本記事を参考に、PL法に関する知識を深め、安全なECサイト運営を心がけてください。
ECサイトの表示に関するご相談・依頼はこちら