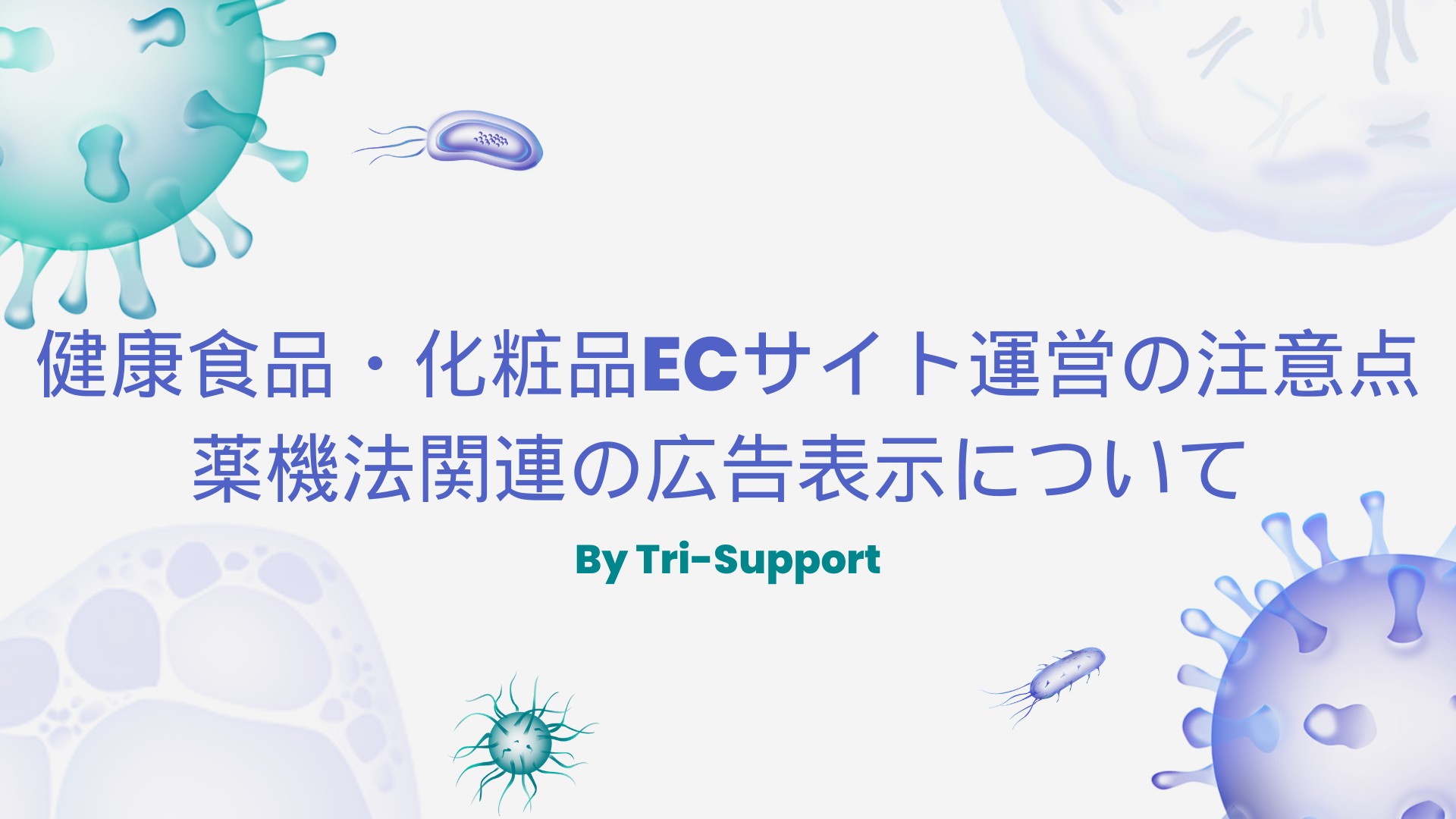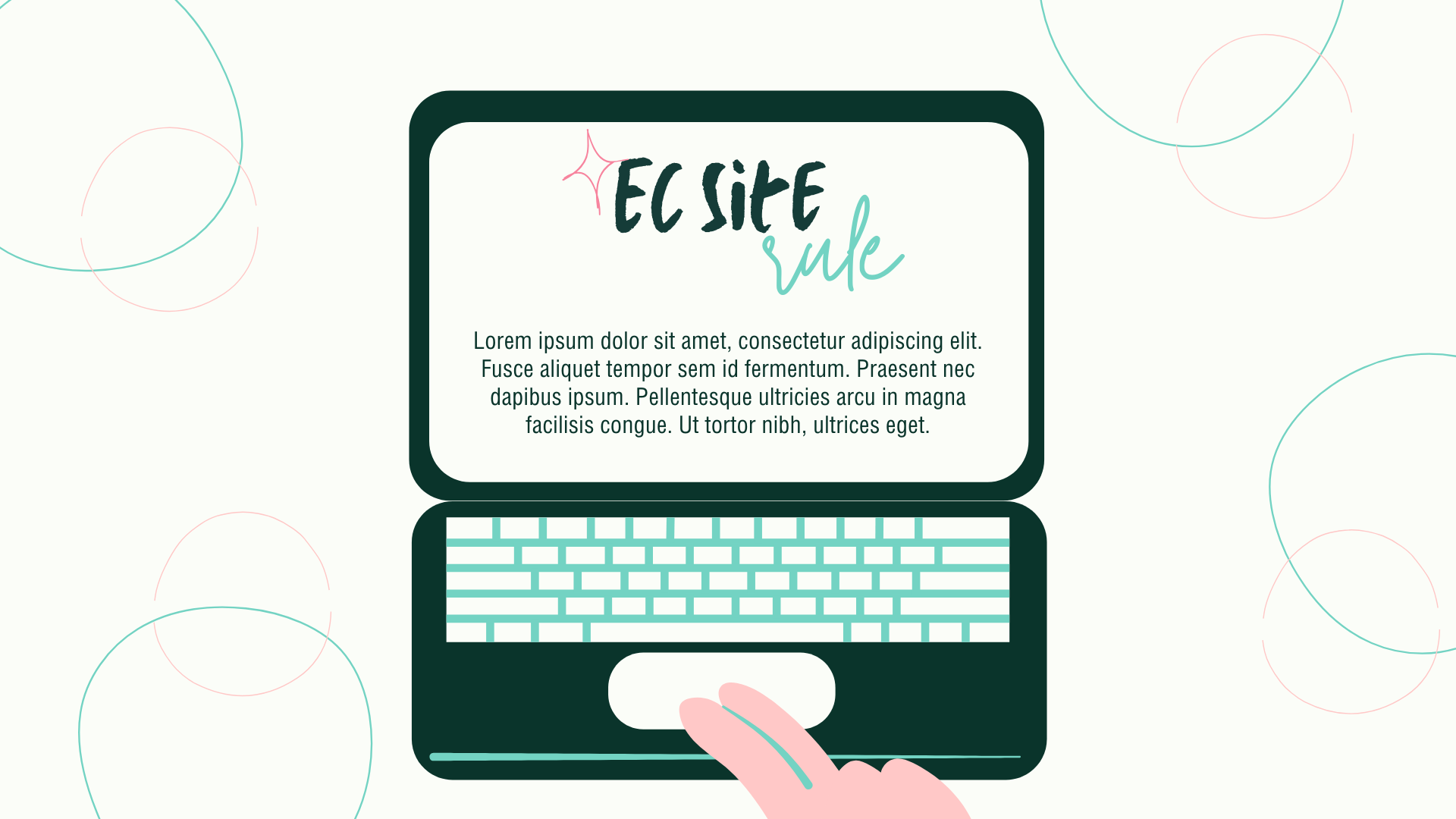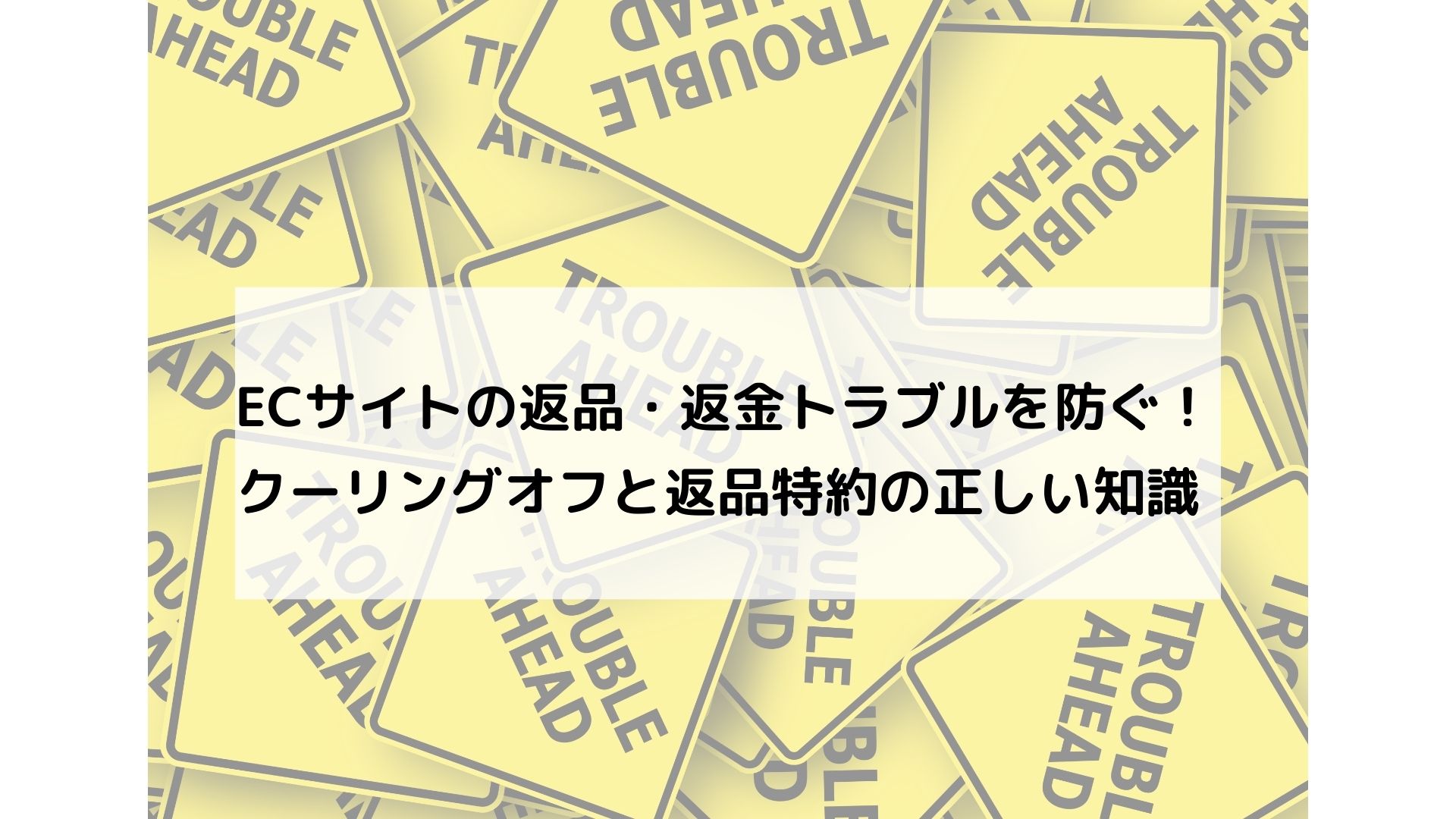健康食品や化粧品のECサイト運営は、美容や健康に関心の高い顧客層にアプローチできる魅力的なビジネスです。
しかし、これらの商品は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)による規制が厳しく、広告表現や販売方法に注意が必要です。
本記事では、薬機法をクリアして売上アップを目指すECサイト運営者向けに、注意すべきポイントを具体的に解説します。
1. 薬機法とは?健康食品・化粧品ECサイト運営における重要性
薬機法は、医薬品、医療機器、化粧品、医薬部外品、再生医療等製品の品質、有効性、安全性を確保するための法律です。
健康食品・化粧品ECサイト運営においては、特に広告表現と販売方法が厳しく規制されています。
1.1. 広告表示の規制
薬機法では、医薬品的な効能効果や、虚偽・誇大な広告表示が禁止されています。
例えば、「〇〇が治る」「〇〇の効果が100%期待できる」といった表現は、薬機法違反となる可能性が高いです。
化粧品は、本来そのほとんどが薬理作用によって効能効果が認められたものではないため、厚生労働省の通知により表現できる内容が決まっています。
例)「頭皮・毛髪を清浄にする」「肌のキメを整える」「爪を保護する」などはOK
1.2. 販売方法の規制
医薬品、医薬部外品、一部の化粧品は、許可を受けた事業者のみが販売できます。
無許可でこれらの商品を販売した場合、薬機法違反となります。
1.3. 違反した場合の罰則
薬機法に違反した場合、行政処分や刑事罰が科される可能性があります。
また、消費者からの信頼を失い、売上にも悪影響が出る可能性があります。
2. 薬機法違反で逮捕も?健康食品・化粧品ECサイト運営者が守るべき広告規制
薬機法違反は、逮捕や刑事罰につながる可能性もある重大な問題です。
健康食品・化粧品ECサイト運営者は、以下の広告規制を遵守する必要があります。
2.1. 医薬品的な効能効果の禁止
健康食品や化粧品は、医薬品的な効能効果を謳うことはできません。
例えば、「塗るだけで美白効果があります」といった表現は、薬機法違反となります。
2.2. 虚偽・誇大広告の禁止
商品の効果や安全性について、虚偽または誇大な広告表示は禁止されています。
例えば、「〇〇の効果が100%期待できる」「副作用は一切ない」といった表現は、薬機法違反となります。
2.3. 使用前・使用後の比較広告の制限
使用前・使用後の比較広告は、誤解を招く可能性があるため、一定の制限があります。
例えば、効果を著しく強調するような比較広告は、薬機法違反となる可能性があります。
2.4. 有名人の推薦・保証の制限
有名人の推薦や保証は、消費者に誤解を与える可能性があるため、一定の制限があります。
例えば、有名人が「私が使って効果がありました」と推薦する場合、その根拠を示す必要があります。
2.5. 医師等の推奨表現の制限
医師や薬剤師などの推奨表現は、消費者に誤解を与える可能性があるため、一定の制限があります。
例えば、医師が「〇〇を推奨します」と推奨する場合、その根拠を示す必要があります。
3. 具体例で解説!薬機法違反となる広告表現・販売方法
薬機法違反となる広告表現や販売方法は、多岐にわたります。
ここでは、薬機法違反となる可能性のある具体的な事例を交えながら、注意すべきポイントを解説します。
3.1. 健康食品の広告表現
- 違反例1: 「飲むだけで痩せる」「〇〇の効果で体脂肪が減少」
- 違反例2: 「〇〇の成分がガンに効果を発揮」「〇〇が認知症を予防」
- 違反例3: 「〇〇を飲んで、1週間で△△kg痩せた」
3.2. 化粧品の広告表現
- 違反例1: 「シミが完全に消える」「シワがなかったことになる」
- 違反例2: 「〇〇の成分が肌の奥深くまで浸透し、細胞を活性化」
- 違反例3: 「〇〇を塗って、1週間で△△歳若返った」
3.3. 販売方法
- 違反例1: 無許可で医薬品や医薬部外品を販売
- 違反例2: 個人輸入した医薬品や化粧品を販売
- 違反例3: 医師の処方箋が必要な医薬品を、処方箋なしで販売
4. 広告表示の違い|特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の違いについて理解しよう
一般的に健康食品と総称される特定の効能を訴求する食品について広告表示を行う際には、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の制度を理解し、適切に活用することで、薬機法に抵触せずに商品の魅力を伝えることができます。
4.1. 特定保健用食品(トクホ)
- 国の審査を受け、特定の保健の効果が科学的に認められた食品です。
- 「お腹の調子を整える」「血圧が高めの方に」など、具体的な保健の効果を表示できます。
- 表示には、消費者庁の許可が必要です。
4.2. 機能性表示食品
- 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示できる食品です。
- 「お腹の調子を整える」「睡眠の質を高める」など、健康の維持・増進に役立つ機能性を表示できます。
- 表示には、消費者庁への届出が必要です。
4.3. 栄養機能食品
- 特定の栄養成分について、国の定めた基準を満たした場合に、その栄養成分の機能を表示できる食品です。
- 「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」など、栄養成分の機能を表示できます。
- 表示には、消費者庁への届出は不要ですが、表示基準に従う必要があります。
取得のハードルで言うと、特定保健用食品>機能性表示食品>栄養機能食品、となります。
事業戦略・商品戦略と併せてこれらの制度を活用することで、健康食品の有効性を適切にアピールし、消費者に安全で信頼性の高い情報を提供することができます。
まとめ
参考リンク
厚生労働省|医薬品等の広告規制についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
厚生労働省|化粧品の効能の範囲について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7518&dataType=1&pageNo=
健康食品・化粧品ECサイト運営において、薬機法は非常に重要な法律です。
薬機法を遵守することで、消費者からの信頼を獲得し、安全な事業運営につなげることができます。
また、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の制度を理解し、適切に活用することで、薬機法に抵触せずに商品の魅力を伝えることができます。
本記事で紹介した内容を参考に、薬機法に関する知識を深め、適切なECサイト運営を行いましょう。
ECサイトの表示に関するご相談・依頼はこちら