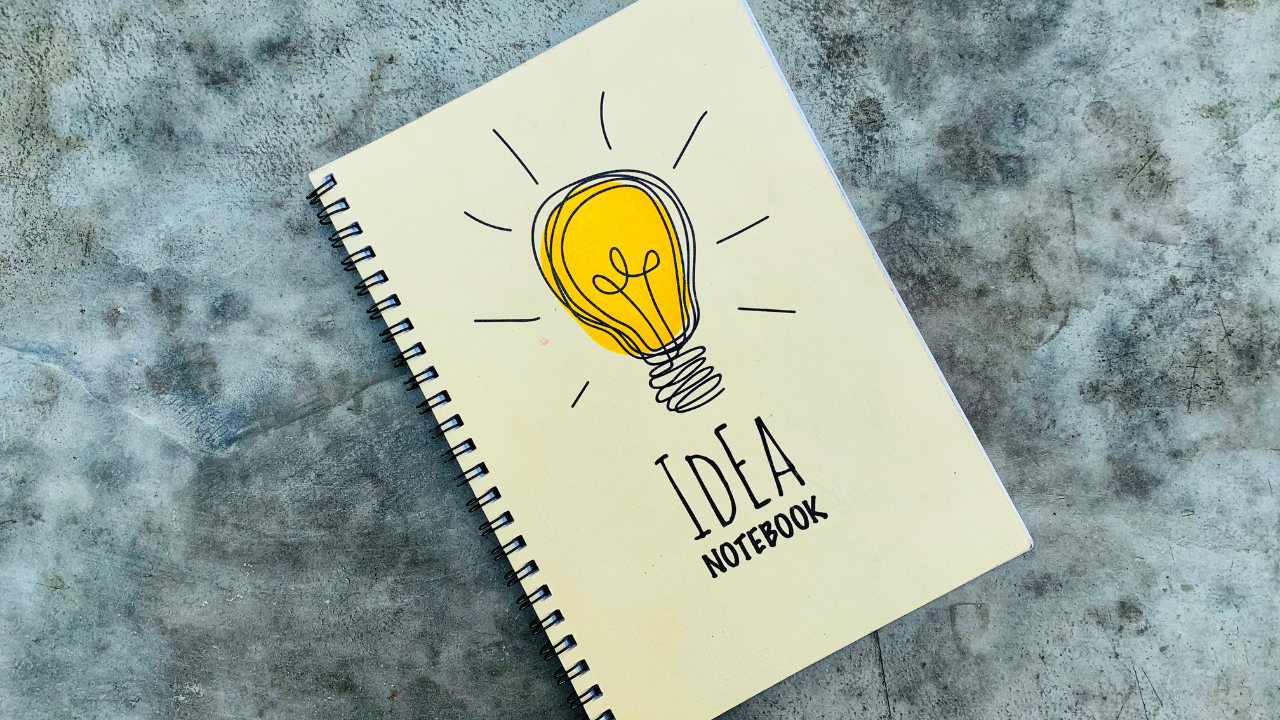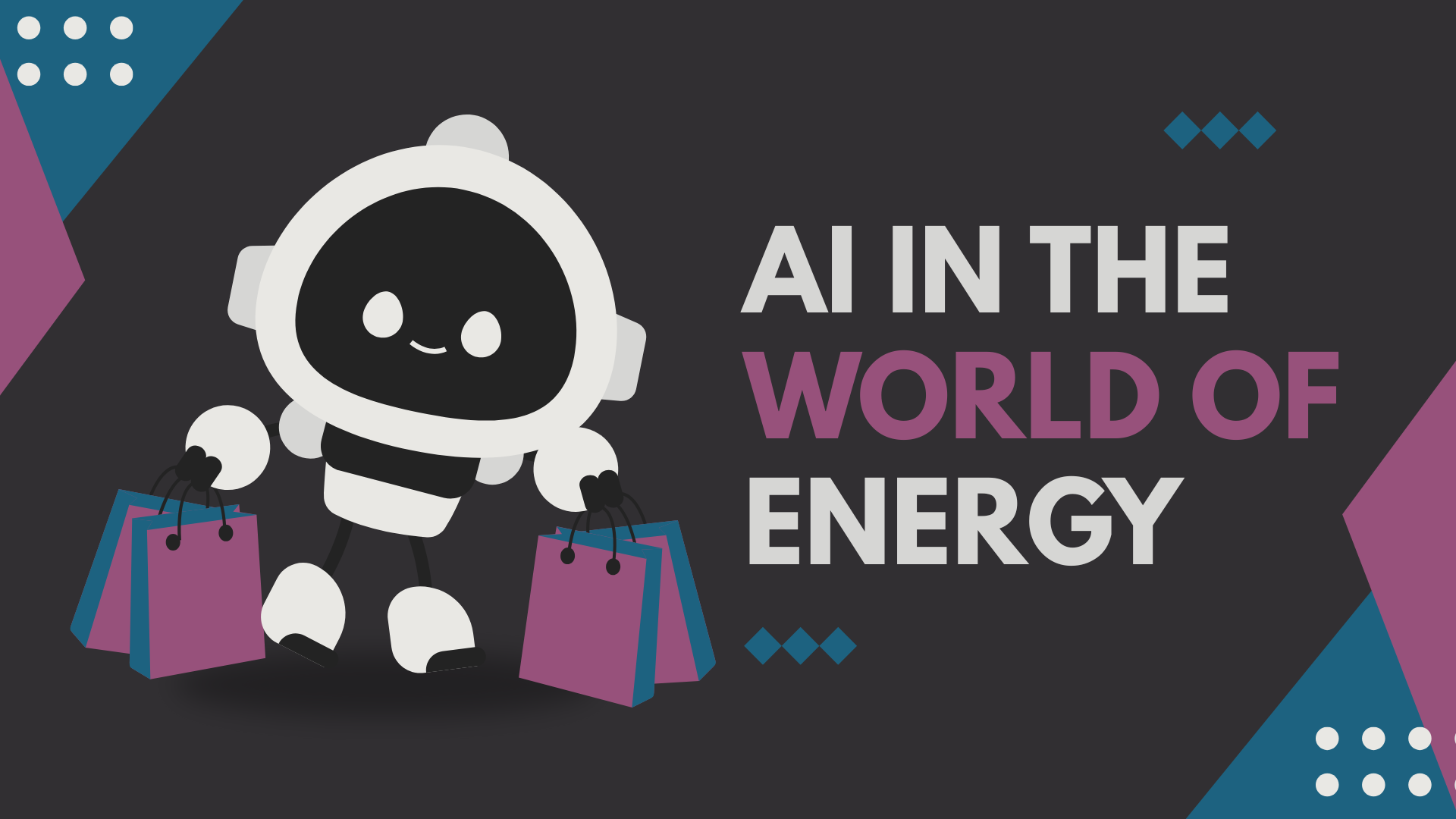電子帳簿保存法とは?中小企業が知るべき基本のキホン
電子帳簿保存法は、1998年に制定された、帳簿や書類を電子データで保存することを認める法律です。
従来の紙での保存義務を緩和し、企業のデジタル化と業務効率化を推進することを目的にしています。
特に2022年1月の改正では、電子取引におけるデータ保存が義務化され、多くの中小企業にとって喫緊の課題となりました。 この法律が対象とするのは、大きく分けて以下の3種類の書類です。
- 電子帳簿・電子書類
会計ソフトで作成した帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)や、パソコンで作成した決算関係書類(損益計算書、貸借対照表など)を指します。
これらは、一定の要件を満たせば電子データのまま保存できます。 - スキャナ保存
紙で受領した国税関係書類(領収書、請求書、契約書など)をスキャンして電子データとして保存することを指します。
これまで紙での保存が原則でしたが、スキャナ保存の要件緩和により、ペーパーレス化を推進しやすくなりました。 - 電子取引データ
電子メールで受領した請求書や領収書、インターネットバンキングの取引履歴、クラウドサービス上で発行された書類など、電子的に授受した取引情報を指します。
2022年1月の改正で、これらは原則として電子データのまま保存することが義務付けられました。
中小企業と電子帳簿保存法との関係
なぜ今、電子帳簿保存法が中小企業にとって重要なのでしょうか?
最大の理由は、2022年1月からの改正によって、電子取引データの保存が義務化されたことにあります。
以前は電子取引データも紙に印刷して保存することが認められていましたが、この特例は廃止されました。
つまり、電子メールで受け取った請求書や、Webサイトからダウンロードした領収書などは、印刷して保存しても法的な要件を満たさず、税務調査で指摘される可能性があるということです。
もちろん、全ての書類を電子データで保存しなければならないわけではありません。
例えば、手書きの領収書や紙で郵送されてきた請求書は、これまで通り紙で保存しても問題ありませんし、スキャナ保存の要件を満たして電子化することも可能です。
重要なのは、電子的にやり取りしたデータは電子的に保存するという原則を理解することです。
この義務化は、中小企業の経理業務に大きな影響を与えます。
従来の紙ベースの業務フローを見直し、電子データに対応した新しい保存体制を構築する必要があるからです。
一方で、これは単に義務が増え手間がかかるようになったというわけではありません。
適切に対応することで、業務効率の向上、コスト削減、そして企業のデジタル化推進といった多くのメリットを享受できるチャンスでもあります。
次章では、中小企業が電子帳簿保存法に対応する上で特に注意すべきポイントについて詳しく解説していきます。
中小企業が電子帳簿保存法に対応する上で注意すべきポイントと保存要件
電子帳簿保存法への対応は、特に今まで紙で帳簿をつけてきた中小企業にとって新たな課題に思えるかもしれません。
しかし、適切な知識と準備があれば、スムーズに移行できます。
ここでは、特に中小企業が注意すべきポイントと、各保存区分における具体的な要件について詳しく解説します。
電子取引データの保存義務化への対応
最も喫緊かつ重要なのが、電子取引データの保存義務化への対応です。
2022年1月以降、電子メール、クラウドサービス、ECサイトなどを通じてやり取りした請求書や領収書などのデータは、原則として電子データのまま保存しなければなりません。
具体的な保存要件としては、以下の3点が挙げられます。
- 真実性の確保
- タイムスタンプの付与
※タイムスタンプ:電子データが作成された日時を証明し、その後改ざんされていないことを保証する技術 - 訂正・削除履歴が残るシステムでの保存
- 訂正・削除の防止に関する事務処理規程の備付けと運用
- 不当な訂正・削除の防止に関する措置
- タイムスタンプの付与
- 可視性の確保
- 関係書類(システム概要書など)の備付け
- 検索機能の確保 ※特に検索機能については、取引年月日、取引金額、取引先で検索できるようにしておくことが必須です。
- ディスプレイやプリンタなどによる出力
- ダウンロードの要求に応じられるようにしておくこと
- 税務調査の際に、電子データをいつでもダウンロードして提供できるようにしておく必要があります。
これらの要件を満たすために、中小企業は以下のいずれかの対応を検討することになります。
- 電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスや会計ソフトの導入
これが最も手軽で確実な方法です。
多くのサービスが上記の要件をクリアしており、導入するだけで法令遵守が可能になります。 - 自社でのシステム構築と事務処理規程の整備
ある程度の規模の企業であれば、自社でシステムを構築し、それに応じた事務処理規程を策定・運用することも可能です。
ただし、専門的な知識が必要となるため、ITコンサルタントや税理士などの専門家の助言を得ることを強くお勧めします。 - 検索要件に対応したファイル名での保存
例えば、「20250705_〇〇株式会社_10000円_請求書.pdf」のように、ファイル名に取引年月日、取引金額、取引先などの情報を付加し、検索性を確保する方法です。
これは最も簡易的な方法ですが、データ量が増えると管理が煩雑になる可能性があります。
スキャナ保存の要件緩和と活用
スキャナ保存は、紙で受領した書類をスキャンして電子データとして保存する方法です。
2022年1月の改正で、以下の点が大きく緩和されました。
- 税務署長による事前承認制度の廃止
これまでスキャナ保存を行うには、事前に税務署長の承認が必要でしたが、これが不要になりました。これにより、より気軽にスキャナ保存を導入できるようになりました。 - タイムスタンプ要件の緩和
タイムスタンプの付与期間が緩和されたほか、訂正・削除履歴が残るシステムで保存する場合や、事務処理規程を整備している場合は、タイムスタンプが不要となりました。 - 検索要件の緩和
売上高1,000万円以下の事業者については、検索要件の一部が免除されるなど、小規模事業者への配慮もなされています。
スキャナ保存は、紙の書類を電子化することで、保管スペースの削減、検索効率の向上、紛失リスクの低減といった多くのメリットをもたらします。
特に、大量の紙書類を扱う業種の中小企業にとっては、業務効率化の大きな一歩となるでしょう。
電子帳簿・電子書類の保存要件
会計ソフトなどで最初から電子データとして作成された帳簿や書類も、電子帳簿保存法の対象です。
これらは、紙に出力せずに電子データのまま保存することが可能です。 主な要件は以下の通りです。
- 真実性の確保:
- 訂正・削除履歴が残るシステムでの保存
- 正規の簿記の原則に従った入力
- 帳簿間の関連性の確保
- 可視性の確保:
- 関係書類の備付け
- 検索機能の確保
- ディスプレイ等による出力
これらの要件は、一般的な会計ソフトを使用していれば、ほとんどの場合満たせるように設計されています。
会計ソフトのデータを適切にバックアップし、いつでも閲覧・出力できる状態を保つことが重要です。
まとめ:自社の状況に合わせた対応を
中小企業が電子帳簿保存法に対応する上で、最も重要なのは、自社の業務フローと現状を正確に把握することです。
- どのような書類を、どのような方法でやり取りしているのか?
- 既存のシステムやツールは電子帳簿保存法に対応しているか?
- 業務フローを変更する必要があるか?
全てを一度に完璧に対応しようとせず、まずは電子取引データの保存義務化に焦点を当て、そこから段階的にスキャナ保存や電子帳簿の保存へと範囲を広げていくのが現実的です。
また、専門家の助言を求めることも非常に有効です。
税理士や行政書士といった士業、会計ソフトのサービスデスクや導入支援など、電子帳簿保存法に関する最新の情報と実践的なアドバイスを受けることができるでしょう。
自社だけで抱え込まず、必要に応じて外部の力を借りることも検討しましょう。
よくあるQ&A
- 電子帳簿保存法に対応しないとどうなりますか
電子取引データを電子保存していない場合、税務調査で指摘を受け、青色申告の承認取り消しになる可能性があります。
青色申告が取り消されると、所得控除や税額控除などのメリットが受けられなくなり、税負担が増えることになります。また、追徴課税の対象となる可能性もあります。
単に罰金が科せられるだけでなく、企業の信頼失墜にもつながるため、必ず対応しましょう。
- 小規模企業でも電子帳簿保存法に対応する必要がありますか?
はい、企業の規模に関わらず、全ての事業者に適用されます。
たとえ個人事業主であっても、電子メールやクラウドサービスで請求書や領収書をやり取りしていれば、電子帳簿保存法の対象となります。
- 電子帳簿保存法に対応するための費用はどれくらいかかりますか?
対応方法によって大きく異なります。
- 最も費用を抑える方法は、ファイル名に規則性を持たせて保存する方法ですが、手間がかかり、データ量が増えると管理が複雑になります。
- クラウド会計ソフトや文書管理システムの導入は、月額数千円〜数万円程度が目安です。
導入費用がかかる場合もありますが、手軽に要件を満たせるため、コストパフォーマンスは高いと言えます。 - 自社でシステムを構築する場合は、開発費用や維持費用が高額になる可能性があります。
自社の規模や予算、現在のIT環境に合わせて、最適な方法を選びましょう。
- 紙で受け取った書類は、すべてスキャンして捨ててしまっても良いですか?
スキャナ保存の要件(真実性、可視性、適正事務処理要件など)を全て満たしていれば、スキャンした紙の書類は破棄しても問題ありません。
しかし、要件を満たしていない場合や、スキャナ保存の対象外となる書類(例:紙で契約した印紙税が課税される契約書の一部など)は、紙での保存が必要です。
中小企業のIT化・DXに関するご相談・依頼はこちら