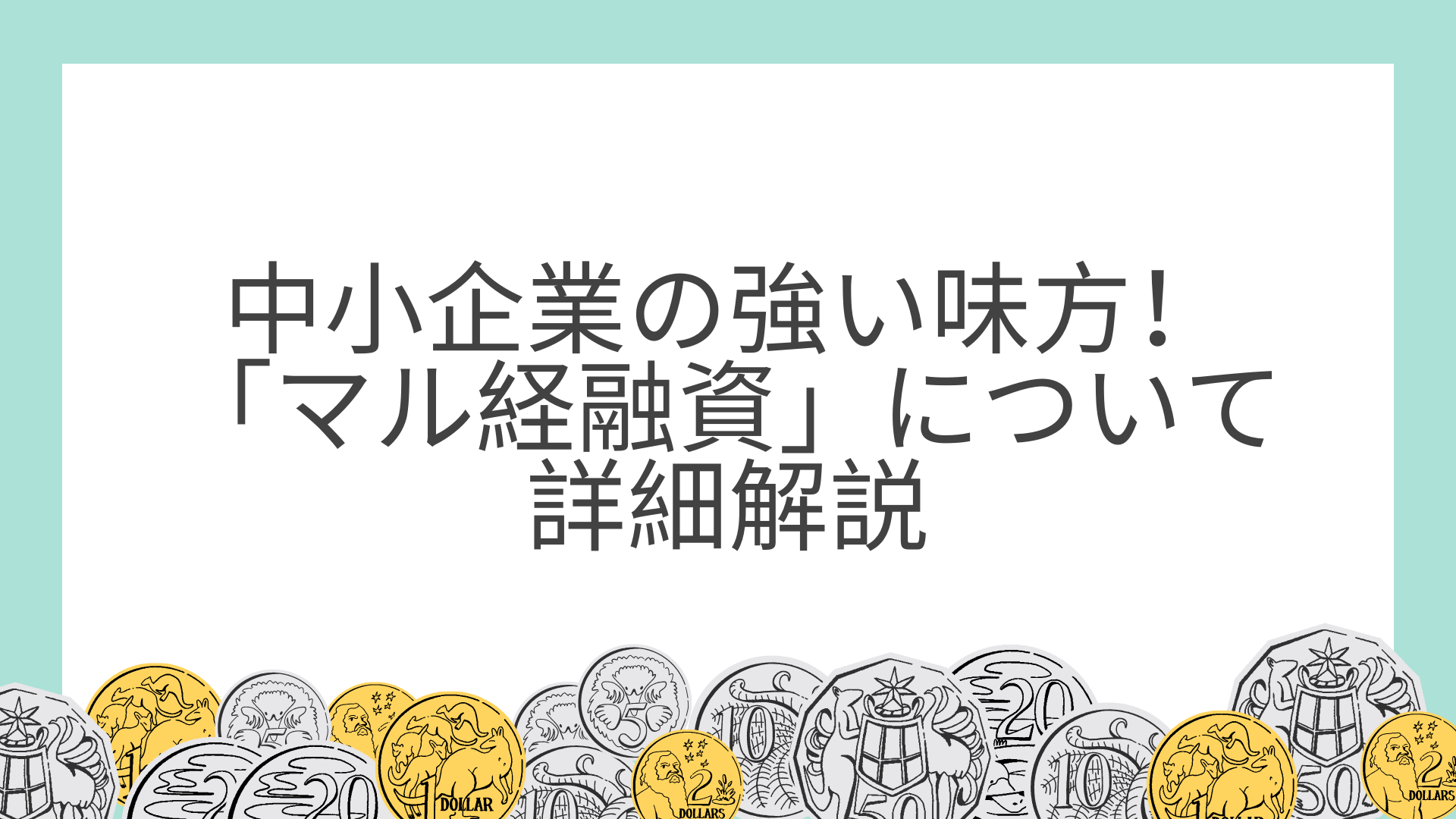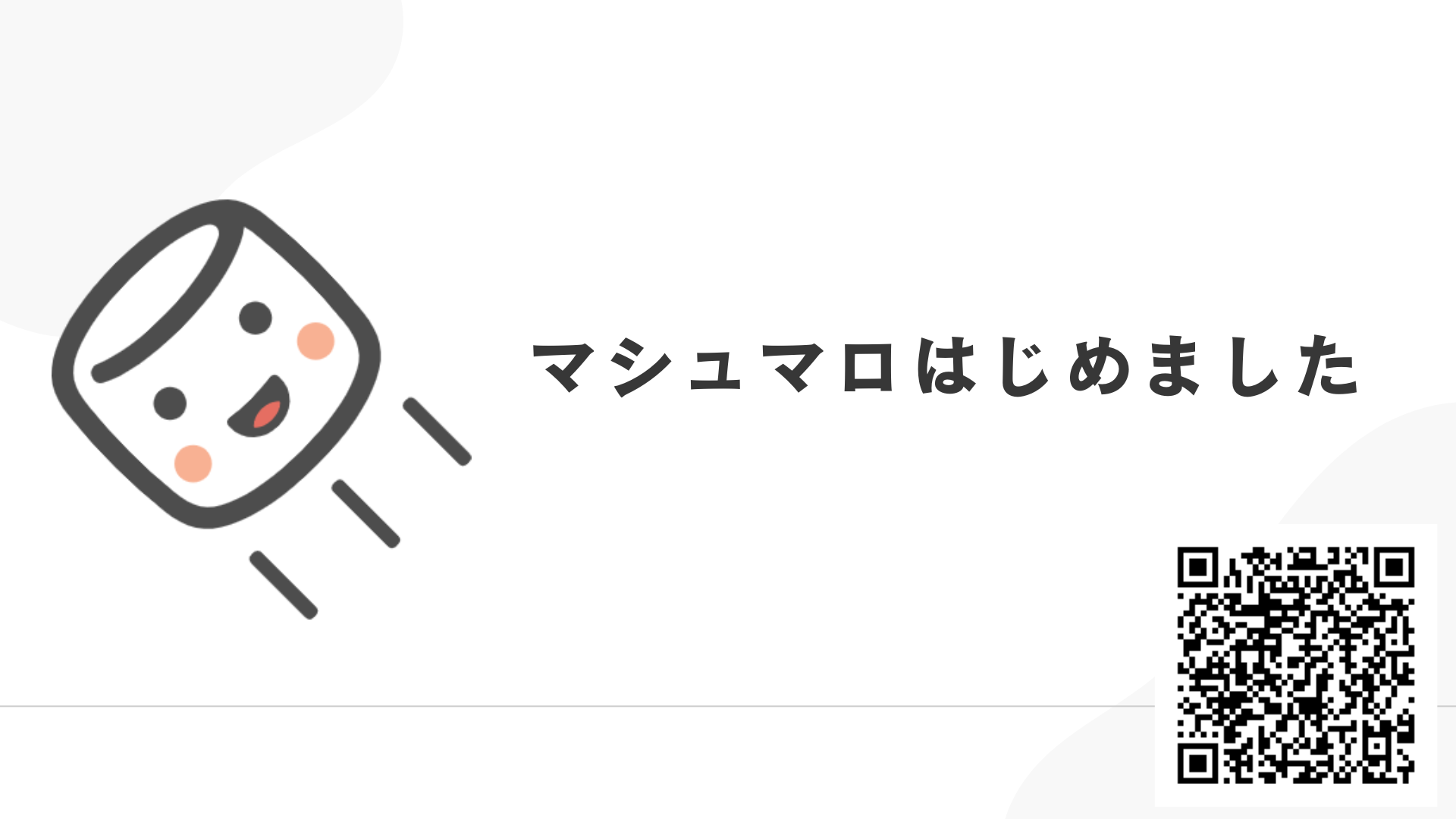はじめに
中小企業の経営者にとって、事業の継続は最大の課題の一つです。
しかし、自然災害や経済状況の変化など、予期せぬ事態に直面することも少なくありません。
このような「もしも」に備えるためには、事前の準備が不可欠です。
本記事では、中小企業の経営者が知っておくべき経営安定関連保証(セーフティネット保証制度)について、初心者にもわかりやすく解説します。
セーフティネット保証制度とは?
セーフティネット保証制度は、中小企業が金融機関から資金を借り入れる際に、信用保証協会が保証人となることで、融資が受けやすくなる制度です。
特に、自然災害や取引先の倒産など、経営に大きな影響を与えるような事態が発生した場合に、中小企業を支援するための制度として注目されています。
信用保証協会とは
信用保証協会とは、金融機関から資金の借り入れなどをする際に、保証人となってくれる機関です。
資金力が弱い中小企業などは、金融機関から借入をしようとしても返済能力が弱く、資金調達が難しい場合がほとんどです。
そのような際に、信用保証協会が保証人となって、融資を受けやすくなるようサポートしてくれるという公的機関です。
参考リンク)全国保証協会連合会
制度の目的
セーフティネット保証制度の目的は、以下の通りです。
- 中小企業の資金調達を円滑化
経営が困難になった中小企業が、迅速に資金を調達できるようにすることで、事業の継続を支援します。 - 経済全体の安定化
中小企業の倒産を防ぐことで、地域経済への波及効果を抑制し、経済全体の安定化に貢献します。
制度の概要
セーフティネット保証制度は取引先の倒産や自然災害など、特定の事由が発生した場合に利用できる保証制度です。
特定の事由としては、以下のような要因が挙げられます。
| 1号認定 | 大型倒産(再生手続き開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者 |
| 2号認定 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者 |
| 3号認定 | 突発的災害(事故等)により影響を受けている特定地域の特定業種を営む中小企業者 |
| 4号認定 | 突発的災害(自然災害等)により影響を受けている特定地域の中小企業者 |
| 5号認定 | 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者 |
| 6号認定 | 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者 |
| 7号認定 | 金融機関の相当程度の経営の合理化(支店の削減等)に伴い借り入れが減少している中小企業者 |
| 8号認定 | RCC(整理回収機構)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者 |
保証限度額
普通保証2億円、無担保保証8,000万円
制度のメリット
セーフティネット保証制度を利用するメリットは、以下の通りです。
- 融資が受けやすくなる
信用保証協会が保証人となるため、金融機関から融資を受けやすくなります。 - 金利が低くなる
一般的な融資に比べて、金利が低い場合があります。 - 手続きが簡素化される
必要な書類が少なく、手続きがスムーズに行えます。
制度の注意点
セーフティネット保証制度を利用しようとした際、注意点としては以下の通りです。
- 利用できる企業が限定される
制度の対象となる企業は、一定の要件を満たす必要があります。
具体的には、セーフティネット保証を利用するには、市(区)町村の担当窓口で認定を受ける必要があります。
認定要件としては、上記の表の通りです。
また、取引先の金融機関に相談に融資の相談をした際、保証協会付融資の提案を受けることもあります。 - 保証料がかかる
信用保証協会に保証料を支払う必要があります。
まとめ
セーフティネット保証制度は、中小企業が「もしも」に備えるための重要な制度です。
本記事で解説した内容を参考に、事前にしっかりと理解しておくことで、いざという時に慌てずに対応することができるでしょう。
本記事が、資金繰りに悩む中小企業の参考になれば幸いです。