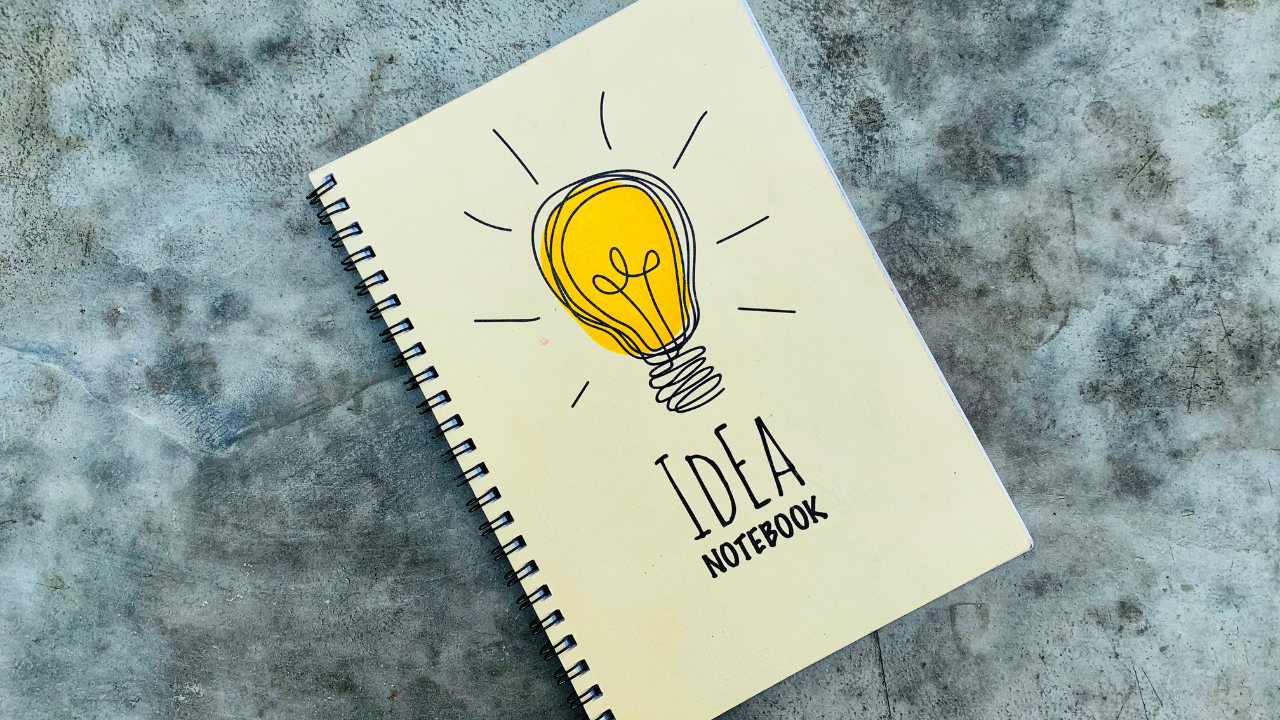電気通信事業法とは?なぜ中小企業が知るべきなのか
電気通信事業法と聞くと、NTTやKDDIのような大手通信事業者のための法律だと思われがちです。
しかし、実はインターネット上でサービスを提供する多くの中小企業にとって、非常に重要な法律なのです。
電気通信事業法の目的と対象
電気通信事業法は、電気通信役務(電気通信サービス)の提供を規律することで、国民の利益を守り、健全な通信事業の発展を促すことを目的としています。
この法律は、単に電話やインターネット回線を提供する事業者だけでなく、以下のようなサービスを提供する事業者も対象となる可能性があります。
- インターネットサービスプロバイダ(ISP)
- クラウドサービス事業者(IaaS、PaaS、SaaSなど)
- IP電話サービス事業者
- レンタルサーバー事業者
- データセンター事業者
- VoIPサービス(050番号等)を提供する事業者
- IoT(モノのインターネット)サービスを提供する事業者
- SNSやマッチングアプリなどのプラットフォーム運営事業者
「うちの会社はただのITサービスを提供しているだけだから関係ない」と思っていませんか?
実は、そのサービスが「他人の通信を媒介する」という機能を持っている場合、電気通信事業法上の規制対象となる可能性が非常に高いのです。
「他人の通信を媒介する」とは?
電気通信事業法における「他人の通信を媒介する」とは、特定の人が送った情報を、別の特定の人に伝える行為を指します。
この「情報」には、音声、データ、画像、テキストなどが含まれます。
- メールの送受信
AさんがBさんに送ったメールを、メールサーバー事業者がBさんに届ける。 - IP電話の通話
Cさんの音声データを、Dさんのスマートフォンに届ける。 - クラウド上のファイル共有
Eさんがアップロードしたファイルを、Fさんがダウンロードできるようにする。
これらの行為は、すべて「他人の通信を媒介する」行為に該当します。
自社サービスでこのような機能を提供している場合、あなたは電気通信事業法上の「電気通信事業者」として、様々な義務を負う可能性があるのです。
中小企業が電気通信事業法を知るべき理由
なぜ、中小企業がこの法律を理解する必要があるのでしょうか。
それは、法律違反が事業継続に大きなリスクをもたらすからです。
- 罰則
無許可で事業を行った場合、罰金や懲役などの罰則が科される可能性があります。 - 行政処分
総務省から事業停止命令などの行政処分を受ける可能性があります。 - 社会的信用の失墜
法律違反が公になれば、顧客からの信用を失い、事業継続が困難になります。 - 事業計画の遅延
許認可が必要な事業であるにもかかわらず、手続きを怠った場合、サービス開始が大幅に遅れる可能性があります。
「知らなかった」では済まされないのが法律です。
特に、新規事業を立ち上げる際には、電気通信事業法に関する事前調査と対応が不可欠です。
本記事を通じて、あなたのビジネスがどのような法的リスクを抱えているのか、そしてどのように対応すべきなのかを理解していただければ幸いです。
許認可の要・不要を分ける「電気通信事業者」の区分と定義
電気通信事業法では、提供するサービスの内容や形態によって、事業者をいくつかの種類に分類しています。
そして、その分類によって、必要な許認可や届出が異なります。
この章では、許認可の要・不要を判断する上で最も重要な「電気通信事業者」の区分と定義について、初心者でも分かりやすく解説します。
第一種電気通信事業者
「第一種電気通信事業者」は、NTTやKDDIのように、自社で「第一種指定電気通信設備」と呼ばれる大規模な通信設備(電話回線、光ファイバーなど)を設置してサービスを提供する事業者を指します。
この事業者は、国のインフラを担う事業者として、総務大臣からの「登録」を受ける必要があります。
登録には、事業計画や財務状況などの厳格な審査があります。
中小企業がこの区分に該当することは稀ですが、自社で大規模な通信インフラを構築する場合は注意が必要です。
第二種電気通信事業者
第二種電気通信事業は、第一種電気通信事業以外の電気通信事業であり、第一種電気通信事業者から電気通信回線設備の提供を受けて、サービスを提供する電気通信事業者のことを指します。
電気通信役務(電気通信サービス)の提供を提供する企業としては、一般的にはこちらに該当すると考えてよいでしょう。
「届出電気通信事業者」と「登録電気通信事業者」
現在の電気通信事業法では、事業者を「登録電気通信事業者」と「届出電気通信事業者」に分類しています。
登録電気通信事業者
これは、「他人の通信を媒介する」サービスを提供するために、「電気通信回線設備を設置する事業者」が該当します。
ここでいう「電気通信回線設備」とは、光ファイバーやメタルケーブル、無線設備などを指します。
- 自社で光ファイバー網を構築して、ISPサービスを提供する事業者
- 自社で基地局を設置して、無線通信サービスを提供する事業者
これらの事業者は、総務大臣への「登録」が必要です。
登録には、事業計画、設備構成、技術基準適合性など、詳細な情報を提出し、審査を受ける必要があります。
届出電気通信事業者
これは、「他人の通信を媒介する」サービスを提供するものの、自社で「電気通信回線設備」を設置せずに、他社の回線設備を借りてサービスを提供する事業者が該当します。
これが、多くのITサービスを提供する中小企業が該当する可能性のある区分です。
- 大手通信事業者の回線を借りて、ISPサービスを提供する事業者
- データセンター事業者の設備を借りて、クラウドサービスを提供する事業者
- 他社の回線を利用して、050IP電話サービスを提供する事業者
これらの事業者は、事業を開始する前に総務大臣への「届出」が必要です。
登録と異なり、審査は不要ですが、届出を怠ると法律違反となります。
「媒介」に該当しないサービス
一方で、以下のようなサービスは、「他人の通信を媒介する」とはみなされず、原則として電気通信事業法の規制対象外となります。
- 情報を一方的に提供するサービス
ウェブサイト、ブログ、ニュースサイトなど、情報を閲覧者に向けて一方的に提供するサービスは、通信の媒介には該当しません。 - 自社の業務連絡
社内の内線電話やチャットツールなど、自社の業務連絡にのみ利用する通信設備は、電気通信事業法上の「電気通信事業」にはあたりません。 - コンテンツ配信サービス
YouTubeやNetflixのように、すでに存在するコンテンツを配信するサービスは、原則として通信の媒介には該当しません。ただし、ライブ配信のようにリアルタイムで通信を媒介する場合は、例外的に規制対象となる可能性もあります。 - 特定のサービスのための限定的な通信
オンラインゲームの対戦や、ウェブ会議システムなど、特定のサービスを提供するために付随的に通信機能を提供する場合は、規制対象外となる可能性があります。ただし、この判断は非常に専門的であり、個別の状況に応じて判断する必要があります。
迷った時の判断基準
あなたのビジネスが「他人の通信を媒介する」に該当するかどうか迷った場合は、以下の点をチェックしてみてください。
- 不特定の第三者が利用できるか?
不特定の人が利用できるサービスであれば、媒介に該当する可能性が高くなります。 - 特定の利用者間で情報のやり取りがあるか?
AさんがBさんに、BさんがAさんに情報を送るような双方向の通信がある場合、媒介に該当する可能性が高くなります。 - 通信の経路を提供しているか?
あなたのサービスが、情報の送り手と受け手を繋ぐ「経路」として機能しているか? これらの質問に「はい」と答える場合、電気通信事業法の規制対象となる可能性が高いです。
届出・登録が必要なビジネスの具体的な例示
この章では、実際にどのようなビジネスが届出や登録を必要とするのか、具体的なビジネスモデルを例に挙げて解説します。
あなたのビジネスに当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてください。
例1)クラウドサービス(IaaS/PaaS/SaaS)
IaaSは、サーバーやストレージ、ネットワークなどのインフラを、顧客に提供するサービスです。
クラウドサービスは、サーバーやストレージ、アプリケーションなどをインターネット経由で提供するサービスです。
このサービス形態は、電気通信事業法の規制対象となる可能性が非常に高いです。
ケース1: IaaS(Infrastructure as a Service)
顧客は、提供されたインフラ上で、自由にアプリケーションを構築・運用します。
この場合、顧客同士の通信を媒介する可能性があるため、「届出電気通信事業者」に該当します。
- レンタルサーバー事業
- VPS(Virtual Private Server)事業
- ホスティング事業
- AWSやGCPのようなクラウド基盤提供事業
これらの事業は、顧客が自由に通信を行うための「経路」を提供しているため、届出が必要です。
ケース2: PaaS(Platform as a Service)
PaaSは、アプリケーション開発のためのプラットフォームを提供するサービスです。
開発者は、提供されたプラットフォーム上でアプリケーションを開発・実行します。
この場合も、開発者同士の通信や、開発したアプリケーションとエンドユーザーの通信を媒介する可能性があるため、「届出電気通信事業者」に該当します。
- アプリケーション開発プラットフォーム
- ウェブサイト構築プラットフォーム
ケース3: SaaS(Software as a Service)
SaaSは、完成されたソフトウェアをインターネット経由で提供するサービスです。
例えば、オンラインストレージサービスやグループウェアなどがこれに該当します。
- オンラインストレージサービス
DropboxやGoogle Driveのように、ユーザーがファイルをアップロード・ダウンロードできるサービスは、「通信の媒介」に該当するため、届出が必要です。 - グループウェア
SlackやMicrosoft Teamsのように、ユーザー間のチャットやファイル共有機能があるサービスは、「通信の媒介」に該当するため、届出が必要です。 - ウェブ会議システム
ZoomやGoogle Meetのように、音声や映像の通信を媒介するサービスは、「通信の媒介」に該当するため、届出が必要です。
判断のポイント
あなたのSaaSサービスに「ユーザー間で情報やファイルをやり取りする機能」があるかどうかをチェックしてください。もしあれば、届出が必要な可能性が高いです。
例2)IP電話サービス
050番号などを利用したIP電話サービスは、電気通信事業法の典型的な規制対象です。
ケース1: 自社で設備を設置する場合
VoIPゲートウェイやSIPサーバーなど、自社でIP電話の通信設備を構築してサービスを提供する場合、「登録電気通信事業者」に該当し、総務大臣への登録が必要です。
ケース2: 他社の設備を借りる場合
大手通信事業者のIP電話基盤を借りて、自社ブランドでIP電話サービスを提供する場合は、「届出電気通信事業者」に該当し、総務大臣への届出が必要です。
例3)IoTサービス
IoT(モノのインターネット)サービスも、電気通信事業法の規制対象となる可能性があります。
ケース1: センサーとサーバー間でデータを収集するだけの場合
センサーが収集したデータを、サーバーに送信して蓄積するだけのサービスは、原則として「他人の通信を媒介する」には該当せず、規制対象外です。
ケース2: ユーザー間でデータを共有する場合
例えば、スマートホームのIoTデバイスで取得したデータを、家族間で共有する機能がある場合、これは「他人の通信の媒介」に該当するため、届出が必要となる可能性があります。
- 家庭用見守りカメラの映像を、離れて暮らす家族と共有するサービス
- スマートロックの開閉履歴を、家族間で共有するサービス
例4: マッチングアプリやプラットフォーム
マッチングアプリやSNSは、原則として「他人の通信を媒介する」に該当しません。
なぜなら、ユーザーが直接通信しているわけではなく、プラットフォーム上で情報をやり取りしているに過ぎないからです。 ただし、例外があります。
- アプリ内でチャット機能を提供している場合
アプリ内でユーザー同士がメッセージをやり取りできる機能がある場合、これは「通信の媒介」に該当します。 - アプリ内で音声通話やビデオ通話機能を提供している場合
これは完全に「通信の媒介」に該当します。 もし、これらの機能を提供している場合は、「届出電気通信事業者」に該当し、届出が必要です。
結論: 「媒介」かどうかの判断は非常に難しい
これらの例からもわかるように、「通信の媒介」に該当するかどうかの判断は、非常に専門的で複雑です。
少しの機能追加やビジネスモデルの変更で、届出や登録が必要になることもあります。
「うちのサービスは大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは非常に危険です。
もし少しでも不安があれば、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
届出・登録手続きの流れと必要書類
ここでは、電気通信事業法の届出・登録手続きの具体的な流れと、必要な書類について解説します。
複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ丁寧に準備すれば、決して難しい手続きではありません。
ステップ1: 事前相談・ビジネスモデルの確認
まず、あなたのビジネスモデルが「届出」または「登録」のどちらに該当するのか、そして本当に電気通信事業法の規制対象となるのかを、総務省や専門家(行政書士)に相談して確認します。
- 総務省への事前相談
総務省の総合通信局では、電話や窓口での事前相談を受け付けています。
具体的なサービス内容を説明し、規制対象となるかどうかの判断を仰ぐことができます。 - 行政書士への相談
行政書士は、あなたのビジネスモデルを詳細にヒアリングし、法的な観点から許認可の要・不要を判断してくれます。
また、必要書類の準備や手続きの代行も依頼できるため、時間と手間を大幅に削減できます。
ステップ2: 必要書類の準備
届出・登録には、以下の書類が必要となります。
届出電気通信事業者の場合(届出) 届出は、比較的シンプルです。以下の書類を準備します。
- 届出書:
- 事業者名、所在地、代表者氏名
- 事業の概要(サービス内容、提供区域など)
- 事業開始予定日
- 利用する回線設備の内容(例:他社の光ファイバー回線を利用)
- 通信の秘密の保護に関する体制(後述)
- 法人登記簿謄本:
- 法人の場合は、発行から3ヶ月以内の登記簿謄本が必要です。
- 事業計画書(任意):
- 届出には必須ではありませんが、総務省に提出する届出書の内容を補足するために、事業計画書を添付することもあります。 登録電気通信事業者の場合(登録) 登録は、届出よりも厳格な審査があります。
以下の書類を準備します。
- 届出には必須ではありませんが、総務省に提出する届出書の内容を補足するために、事業計画書を添付することもあります。 登録電気通信事業者の場合(登録) 登録は、届出よりも厳格な審査があります。
- 登録申請書:
- 事業者名、所在地、代表者氏名
- 事業の概要
- 電気通信設備設置の計画(設備の構成図、設置場所など)
- 事業収支の見込み
- 役員名簿
- 事業計画書:
- 事業の概要、サービス内容、提供区域、料金などを詳細に記載します。
- 設備概要図:
- 自社で設置する通信設備の構成図、設置場所、設備のスペックなどを詳細に記載します。
- 通信の秘密の保護に関する体制:
- 通信の秘密を保護するための社内体制や規程を記載します。
- 財産的基礎を証明する書類:
- 貸借対照表、損益計算書など、事業を継続するための財務的な安定性を示す書類が必要です。
- 役員に関する書類:
- 役員が欠格事由に該当しないことを証明する書類が必要です。
- その他総務大臣が指定する書類
ステップ3: 総務省への提出
書類がすべて準備できたら、事業者の本店所在地を管轄する総合通信局に提出します。
- 届出の場合: 提出後、特に問題がなければ、数日〜数週間で届出が受理されます。
- 登録の場合: 提出後、総務省による厳格な審査が行われます。審査には数ヶ月かかることもあります。
ステップ4: 届出受理・登録完了
届出が受理されるか、登録が完了すれば、晴れて電気通信事業者として事業を開始することができます。
当事務所へのご依頼の流れ
当行政書士事務所では、電気通信事業法に関する許認可手続きについて、以下のような流れでサポートさせていただきます。
- お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。 - 無料相談(ヒアリング)
当事務所の行政書士が、あなたのビジネスモデルについて詳細にヒアリングさせていただきます。
この段階で、許認可の要・不要について、ある程度の見通しをお伝えします。 - 正式なご契約
ヒアリング後、サポート内容とお見積もりをご提示します。ご納得いただけましたら、ご契約となります。 - 書類作成・手続き代行
ご契約後、当事務所にて必要書類の作成を進めます。 - 届出受理・登録完了
無事に手続きが完了したら、事業開始となります。
おわりに
電気通信事業法の許認可手続きは、事業の成功を左右する重要なステップです。
「うちのビジネスは関係ないと思っていたけど、もしかして…」
「手続きが複雑で、どこから手をつけていいか分からない…」
もしあなたがこのように感じているなら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
あなたの新しいビジネスが、法律を遵守し、安心して成長していけるよう、全力でサポートいたします。
電気通信事業法に関するご相談・依頼はこちら