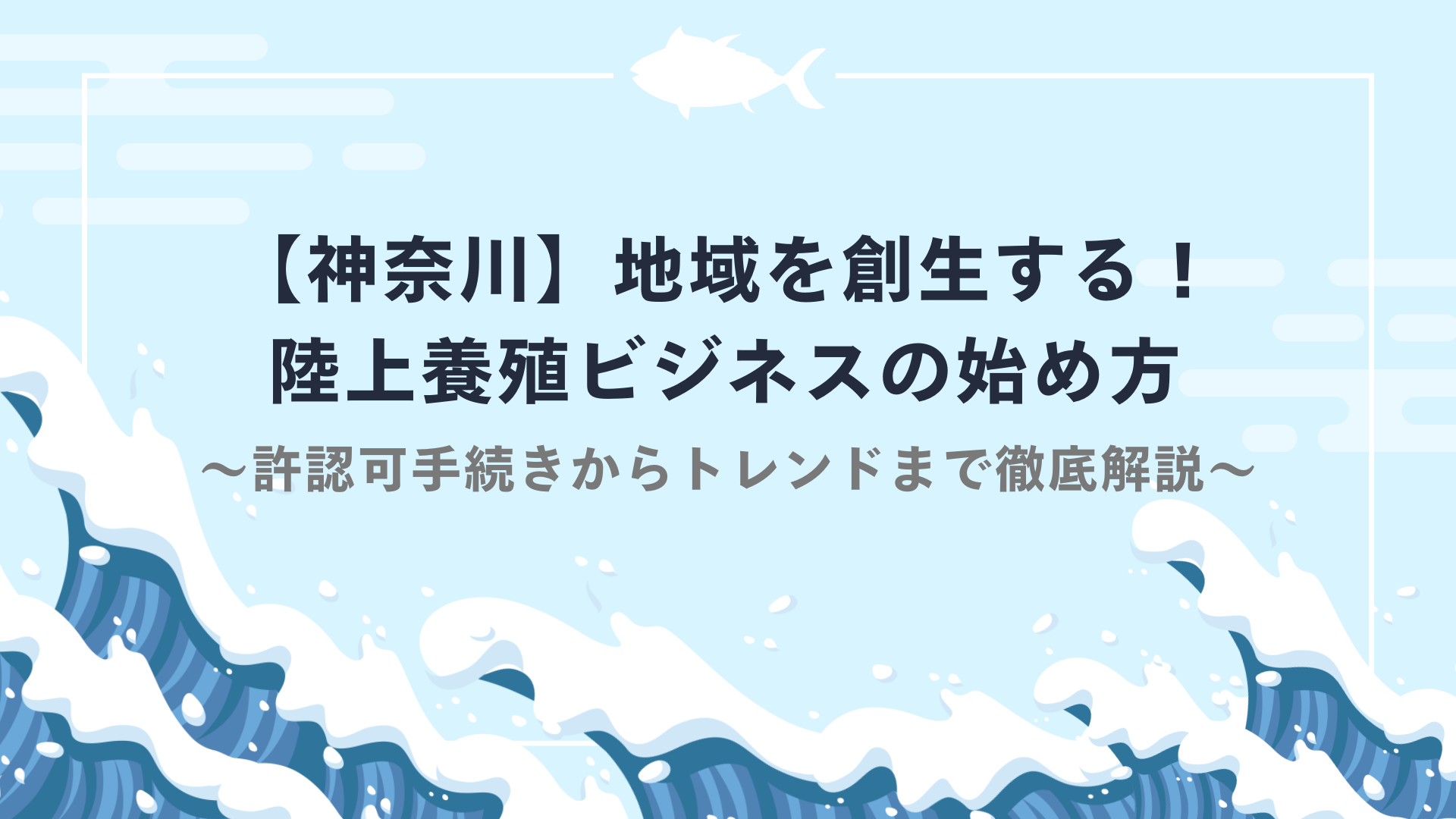陸上養殖とは?|地域創生と持続可能な水産ビジネスの可能性
陸上養殖の定義と仕組み
陸上養殖とは、陸上に設置された閉鎖的な環境で魚介類を飼育する養殖方法です。
従来の海上養殖とは異なり、水温や水質を人工的に制御できるため、天候や自然環境に左右されずに安定した生産が可能です。
また、排水処理システムを導入することで、環境負荷を低減し、持続可能な水産ビジネスを実現できます。
具体的な仕組みとしては、以下の3つの要素が重要です。
- 閉鎖循環式システム
飼育水を浄化・再利用することで、水の使用量を大幅に削減します。
例えば、一般的な陸上養殖では、1kgの魚を生産するのに必要な水量は、従来の養殖方法の10分の1以下に抑えることが可能と言われています。 - 高度な水質管理
水温、pH、溶存酸素量などを常に最適な状態に保つことで、魚のストレスを軽減し、成長を促進します。 - 自動給餌システム
魚の成長段階や食欲に合わせて、適切な量の飼料を自動的に与えることで、飼料効率を高め、廃棄物を削減します。
陸上養殖のメリット
- 安定供給
天候や自然環境に左右されず、年間を通して安定した生産が可能です。
例えば、台風や赤潮などの影響を受けやすい海上養殖では、年間を通しての生産量が大きく変動する可能性がありますが、陸上養殖では年間を通して安定した生産が可能です。 - 高品質
水温や水質を適切に管理することで、高品質な魚介類を生産できます。
例えば、閉鎖循環式システムでは、寄生虫や病原菌の侵入を防ぎ、安全性の高い魚を生産できます。 - 環境負荷の低減
排水処理システムにより、環境への負荷を低減できます。
例えば、排水中の窒素やリンの濃度を大幅に低減し、水質汚染を防止できます。 - 地域活性化
地域資源を活用し、新たな産業を創出することで、地域経済の活性化に貢献できます。
例えば、耕作放棄地や遊休施設を活用した陸上養殖施設の建設は、地域の雇用創出や税収増加につながります。 - トレーサビリティの確保
生産履歴を管理しやすく、消費者に安全・安心な魚介類を提供できます。
例えば、ブロックチェーン技術を活用することで、生産から消費までの履歴を透明化し、消費者の信頼を得ることができます。
陸上養殖のデメリット
- 初期投資コスト
施設建設や設備導入に多額の初期投資が必要です。
例えば、1,000トン規模の陸上養殖施設を建設する場合、数億円から数十億円の初期投資が必要となることがあります。 - 運営コスト
水温・水質管理や飼料費など、運営コストがかかります。
例えば、電気代や飼料代は、生産コストの大部分を占めます。
また、水温・水質管理をするための機械が故障したり停電して動かなくなった場合、全滅の危険性もあります。 - 高度な技術
水質管理や魚病対策など、高度な知識と技術が必要です。
例えば、閉鎖循環式システムでは、水質管理の専門家や魚病診断の専門家が必要です。
地域創生における陸上養殖の役割
陸上養殖は、地域資源を活用し、新たな産業を創出することで、地域経済の活性化に貢献できます。例えば、以下の取り組みが考えられます。
- 耕作放棄地や遊休施設の活用
使われなくなった農地や工場などを陸上養殖施設に転換することで、地域の活性化に貢献できます。 - 地域ブランドの確立
地域固有の魚種や養殖技術を活かしたブランドを確立することで、高付加価値化を図り、地域経済の活性化に貢献できます。
例えば、サーモンや海ぶどう、バナメイエビなどを陸上養殖で養殖している企業も存在します。 - 観光資源との連携
陸上養殖施設を観光資源として活用し、地域への集客力を高めることで、地域経済の活性化に貢献できます。
持続可能な水産ビジネスとしての陸上養殖
世界的な人口増加や気候変動により、水産資源の枯渇が懸念されています。
陸上養殖は、環境負荷を低減し、持続可能な水産ビジネスを実現するための有効な手段です。
閉鎖的な環境で飼育することで、海洋汚染や生態系への影響を抑制し、資源の持続的な利用に貢献できるといわれています。
一方で、水産庁の調査では、100トン以上の生産規模を持つ陸上養殖事業者は全体の4%。
約9割が生産規模50トン未満の中小事業者だという傾向が出ています。
※25mプールの水量が「360t」なので、その6分の1程度の大きさの水槽のイメージです
神奈川県における陸上養殖の現状|市場、課題、そして未来
神奈川県の漁業の現状
神奈川県は、相模湾や東京湾などの豊かな漁場に恵まれ、多様な魚介類が水揚げされています。
しかし、近年は漁獲量の減少や漁業者の高齢化・後継者不足などが課題となっています。
- 漁獲量の減少
神奈川県の漁獲量は、1980年代には年間約20万トンありましたが、近年は約4万トンにまで減少しています。 - 漁業者の高齢化
神奈川県の漁業者の平均年齢は60歳を超えており、後継者不足が深刻化しています。 - 水産資源の減少
地球温暖化や海洋汚染などの影響により、水産資源が減少しています。
神奈川県における陸上養殖の可能性
神奈川県は、都市部に近い立地や交通アクセスの良さなど、陸上養殖に適した条件を備えています。
また、県内には水産技術センターや大学などの研究機関があり、技術支援や人材育成が期待できます。
- 都市部へのアクセス
神奈川県は、東京や横浜などの大都市に近く、新鮮な魚介類の需要が高いといえます。 - 交通インフラ
神奈川県は、高速道路や鉄道などの交通インフラが整備されており、全国各地への輸送が容易です。 - 研究機関
神奈川県には、水産技術センターや東京大学などの研究機関があり、陸上養殖に関する研究開発が進んでいます。
神奈川県における陸上養殖の課題
- 土地の確保
都市部に近いことから、陸上養殖施設の建設に適した土地の確保が難しい場合があります。 - エネルギーコスト
水温・水質管理に多量のエネルギーを消費するため、エネルギーコストの削減が課題です。 - 人材育成
陸上養殖に関する専門知識や技術を持つ人材の育成が必要です。
神奈川県における陸上養殖の未来
神奈川県では、陸上養殖を新たな水産ビジネスとして推進し、地域経済の活性化や持続可能な水産資源の利用を目指しています。
スマート技術の導入や地域資源の活用など、新たな取り組みが進められています。
- スマート養殖の推進
IoTやAIなどの技術を活用し、生産性の向上やコスト削減を目指します。 - 地域資源の活用
未利用の地域資源(温泉水、工場排水など)を活用し、環境負荷の低減やコスト削減を目指します。 - 6次産業化の推進
陸上養殖で生産した魚介類を加工・販売することで、高付加価値化を図ります。
陸上養殖ビジネスを始めるための許認可手続き|必要な書類、申請の流れ、注意点
陸上養殖に必要な許認可
陸上養殖を始めるには、様々な許認可が必要です。主な許認可は以下の通りです。
- 養殖業の届出
令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の実施にあたり知事への届出が必要となりました。 - 水質汚濁防止法に基づく排水基準の遵守
排水処理施設の設置や排水基準の遵守が必要です。 - 建築基準法に基づく建築確認
陸上養殖施設の建設には建築確認が必要です。 - 食品衛生法に基づく営業許可
生産した魚介類を販売するには営業許可が必要です。
直接的には必要となるのは「養殖業の届出」ですが、事業を営むにあたっては上記のような許認可が必要となってきます。
許認可手続きの流れ
許認可の一般的な流れとしては、以下のような流れとなります。
特に、許認可には時間がかかる場合が多く、かつ施設の建設や設備の導入にも関わってくるため、できるだけ早い段階で専門家へ相談することをおススメします。
- 事前相談: 関係機関に相談し、必要な許認可や手続きを確認します。
- 事業計画の策定: 事業計画を策定し、許認可に必要な書類を作成します。
- 申請: 関係機関に申請書類を提出します。
- 審査: 関係機関による審査が行われます。
- 許可: 審査に合格すると、許可が交付されます。
参考)神奈川県|陸上養殖が届出制になりました!https://www.pref.kanagawa.jp/docs/kb2/todokedeyoushoku.html
まとめ
地球の温暖化や水温上昇、自然環境の変化に伴い、安定的に水産資源を生産できる陸上養殖は今後も市場規模の拡大が見込まれています。
地方創生やSDGsにも貢献できるビジネスモデルですので、興味のある事業者の方はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
起業に関するご相談はこちら