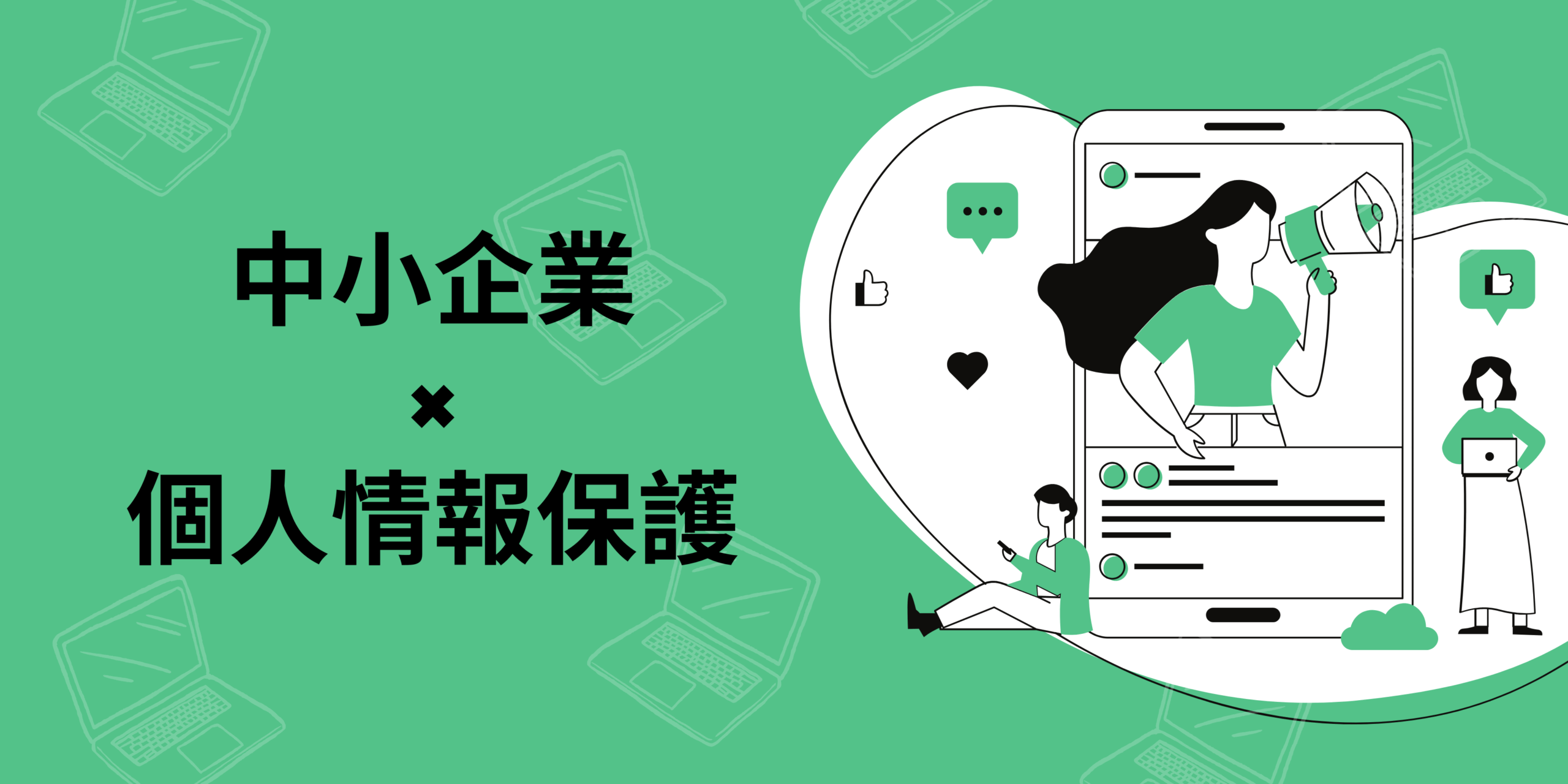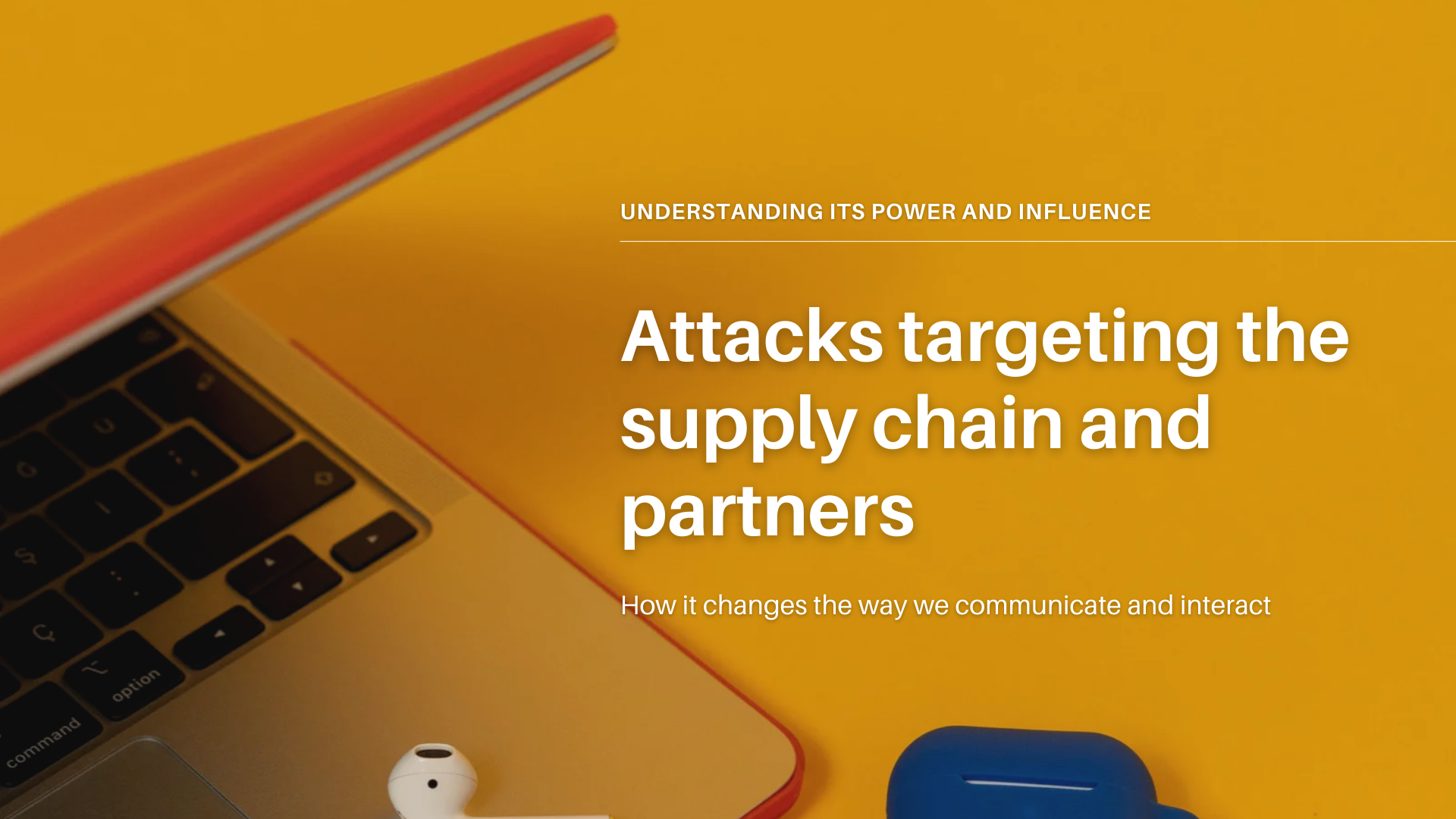昨今はプライバシー意識の高まり、インターネットの更なる進化に伴って、「個人情報」について厳格な管理が求められるようになってきました。
一方で、中小企業では「個人情報の管理、どこまでやればいいんだろう?」と悩む経営者も多いのではないでしょうか。
しかし、個人情報の適切な管理は、企業の信頼性に関わる重要な課題です。
本記事では、中小企業の皆様が安心して個人情報を取り扱えるよう、どのような情報を、どうやって管理すれば良いのかについて、具体的な指針を簡潔に解説します。
中小企業が知っておくべき個人情報保護法の基本原則
企業が取り扱う個人情報については、個人情報保護法の規制を受けます。
個人情報保護法は個人情報の適正な取り扱いを義務付ける法律であり、中小企業も例外なく適用されます。
そもそも個人情報とは?
個人情報とは、氏名、生年月日、電話番号などで特定の個人を識別できる情報すべてを指します。
ウェブサイトの閲覧履歴なども、他の情報と組み合わせることで個人を特定できる場合、個人情報とみなされます。
個人情報保護法の5つの基本原則
個人情報保護法は、個人情報を適切に扱うための以下の5つの原則を定めています。
- 利用目的の特定と通知・公表
個人情報を使う目的を明確にし、本人に伝える(または公表する)。 - 適正な取得
不正な手段で個人情報を取得しない。 - 利用目的の範囲内での利用
特定した目的以外に個人情報を利用しない。 - 安全管理措置
情報漏洩などを防ぐための対策を講じる。 - 第三者提供の制限
原則として本人の同意なしに第三者に情報を提供しない。
中小企業では、個人情報保護に関する意識の低さ、専門知識やリソース不足、アナログ管理、セキュリティ対策の甘さが課題になりがちです。
これらの基本原則を理解し、自社の状況と照らし合わせながら対策を進めることが重要です。
どんな個人情報を管理すべきか?中小企業が保有する情報の洗い出し
個人情報保護の第一歩は、自社がどのような個人情報を、どこに、どれくらいの期間、どのような形態で保有しているかを正確に把握することです。
主な個人情報の種類
- 顧客情報
氏名、住所、電話番号、購買履歴、クレジットカード情報、問い合わせ履歴など。顧客管理システムやExcel、紙媒体で管理されていることが多いでしょう。 - 従業員情報
氏名、住所、生年月日、電話番号、マイナンバー、雇用契約書、給与明細、健康診断結果など。特にマイナンバーは「特定個人情報」として厳格な管理が必要です。 - 採用応募者情報
氏名、履歴書、職務経歴書、選考結果など。不採用の場合は、一定期間経過後に適切に廃棄または消去する必要があります。 - その他
取引先担当者情報、セミナー参加者情報、防犯カメラの映像なども個人情報になり得ます。
情報の洗い出しとマッピングの重要性
これらの個人情報をすべて洗い出し、「どのような情報か」「どこに保管されているか」「誰がアクセスできるか」「どのような形態か」「いつまで保管するか」を明確にすることで、管理体制構築の道筋が見えてきます。
まずはExcelなどで一覧化することをお勧めします。
個人情報をどうやって管理すれば良いか?中小企業向け安全管理措置のポイント
個人情報保護法では、事業者に個人情報の安全管理措置を義務付けています。
中小企業でも実践できる現実的な対策を、組織的、人的、物理的、技術的の4つの側面から解説します
組織的安全管理措置
個人情報保護のための社内体制やルールを整備します。
- 個人情報保護責任者の任命
責任者を明確に定め、社内ルールの策定や指導を行います。 - 個人情報取扱規程の策定
個人情報の取得、利用、保管、廃棄などの具体的なルールを定めます。 - 個人情報に関する台帳の整備
どこにどのような個人情報があるかを常に把握します。 - 定期的な見直しと改善
法改正や業務内容の変化に応じて、体制や規程を見直します。
人的安全管理措置
従業員への教育や監督を通じて、個人情報の適切な取り扱いを徹底します。
- 従業員への教育・研修の実施
個人情報保護法の基本や社内ルールについて、定期的に研修を行います。 - 秘密保持に関する誓約書の締結
従業員との間で秘密保持の誓約書を交わします。 - 従業員の監督
不適切な取り扱いがないかチェックし、必要に応じて指導を行います。
物理的安全管理措置
個人情報が記録された媒体を物理的に保護します。
- 入退室管理の徹底
個人情報を取り扱う場所への入退室を制限します。 - 盗難等からの保護
書類やPC、USBメモリなどは施錠できる場所に保管します。 - 持ち出し制限
個人情報の社外への持ち出しを原則禁止し、許可制とします。 - 廃棄・消去の確実な実施
不要な個人情報は、復元不可能な方法で確実に廃棄・消去します。
技術的安全管理措置
情報システムやネットワークにおける個人情報の保護対策です。
- アクセス制御の実施
システムへのアクセス権限を必要最小限の者のみに限定します。 - 不正アクセス・不正ソフトウェア対策
ファイアウォール、ウイルス対策ソフトを導入し、常に最新に保ちます。 - 暗号化対策
個人情報を含むデータを送受信する際は暗号化通信を利用し、保管時も暗号化を検討します。 - バックアップと復旧
定期的にバックアップを取り、災害時にも復元できるようにします。 委託先の監督 外部業者に個人情報の取り扱いを委託する場合は、委託元にも監督義務が生じます。信頼できる業者を選び、契約書に安全管理に関する条項を盛り込み、定期的に管理状況を確認しましょう。
とはいえ、人的・物理的リソースが不足しがちな中小企業にとっては、すべてを完璧に対応することは難しいかもしれません。
例えば大企業では、個人情報を取り扱う業務を行うエリアは生体認証などで入退室管理するなど、大規模な管理を行う場合もありますが、中小企業においてはそこまで管理することは困難でしょう。
そのような場合、例えば個人情報が記載された紙媒体は施錠されたキャビネットに保管し、個人情報保護責任者が鍵管理するなど、できる範囲内で管理をしっかり行うと良いでしょう。
個人情報保護のための具体的な社内規定とプライバシーポリシーの作成
個人情報の適切な管理には、社内ルール作りと、顧客や外部への情報開示が不可欠です。
社内規定(個人情報取扱規程)の重要性
社内規定は、従業員が個人情報をどのように取り扱うべきかを具体的に定めた内部のルールブックです。
情報漏洩のリスクを減らし、責任を明確化するために必要です。
- 主な項目
目的、用語の定義、個人情報保護体制、取得・利用・保管・廃棄・第三者提供に関するルール、開示・訂正・利用停止等の請求への対応、罰則規定など。 - 作成時のポイント
自社の実態に合わせ、分かりやすく記述し、全従業員に周知徹底します。
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)の作成
プライバシーポリシーは、企業が個人情報をどのように取り扱うかを社外に公表する方針です。
企業の透明性と信頼性を示すために重要です。
- 主な項目
基本方針、取得する個人情報の種類と利用目的、安全管理措置の概要、第三者提供について、開示・訂正・利用停止等について、問い合わせ窓口など。 - 作成時のポイント
ウェブサイトに掲載し、法令を遵守し、企業の姿勢を明確に示します。
社内規定とプライバシーポリシーは、個人情報保護体制を支える重要な要素です。
これらを適切に整備し、運用することで、リスクを効果的に低減できます。
情報漏洩が起きたらどうする?中小企業が備えるべき緊急時の対応と日頃からの意識
どんなに厳重な対策を講じていても、情報漏洩のリスクを完全にゼロにすることはできません。
万が一、情報漏洩が発生した場合の対応の速さが、企業の存続に影響を与えます。
情報漏洩発生時の緊急対応フロー
- 事実関係の確認と被害状況の把握
どのような情報が、どのように漏洩し、どれくらいの範囲に影響があるかを特定し、証拠を保全します。 - 被害拡大の防止
システムの停止、パスワード変更、媒体の回収などを行い、これ以上の情報流出を阻止します。 - 関係各所への連絡・報告
- 社内への報告 経営層や個人情報保護責任者へ速やかに報告。
- 個人情報保護委員会への報告 原則として義務付けられています。
- 本人への通知 漏洩した個人情報の本人へ、状況と対応策を通知します。
- 関係機関への連絡 警察、取引先、場合によっては報道機関へも連絡します。
- 再発防止策の検討と実施
漏洩原因を究明し、具体的なシステム改修や社内ルールの見直し、従業員教育などを実施します。 - 事後対応と評価
損害賠償、風評被害対策、顧客対応を行い、今後の危機管理体制に活かします。
日頃からの意識と準備
情報漏洩は「起こるもの」という前提で、以下の準備をしておくことが重要です。
- 危機管理意識の醸成
経営層から従業員まで、全員が高い意識を持つ。 - 情報漏洩対応マニュアルの作成
緊急時の対応フローを定めたマニュアルを事前に作成し周知する。 - 定期的な訓練の実施
マニュアルに基づき、情報漏洩を想定した訓練を行う。 - 外部専門家との連携
行政書士や弁護士、ITセキュリティ専門家と連携体制を構築しておく。 - サイバー保険の検討
発生しうる費用リスクに備え、加入を検討する。
情報漏洩は企業の信頼性を揺るがす重大な事故です。日頃からの意識と準備を徹底し、万が一の事態に備えることが、持続的な事業運営のために不可欠です。
特に、実際に情報漏洩が起こってしまった場合、その影響範囲の特定や技術上の原因の突き止めには、自社のみでは対応が困難な場合も多くあります。
情報漏洩が起こってしまった場合の対応専門のITセキュリティベンダなどもありますので、事前に連携体制を構築しておくことが重要です。
まとめ|中小企業こそ個人情報保護の徹底を
本記事では、中小企業が個人情報をどこまで、そしてどのように管理すれば良いのかを簡潔に解説しました。
中小企業であっても個人情報保護法は完全に適用されます。
本記事でご紹介した「情報の洗い出し」「社内規定とプライバシーポリシーの作成」「安全管理措置の実施」「緊急時の対応計画」といった基本を確実に押さえることで、情報漏洩のリスクを大幅に低減し、万が一の事態にも適切に対応できる体制を構築できます。
個人情報の適切な管理は、顧客や従業員からの信頼を獲得し、企業のブランドイメージを高め、ひいては持続的な事業成長に繋がる重要な経営戦略です。

サービス紹介|当事務所にご相談ください
当事務所ではITに精通した行政書士により、中小企業の個人情報保護について支援しています。
- 個人情報保護法に関するアドバイス
- 個人情報取扱規程(社内規定)の作成支援
- プライバシーポリシーの作成支援
- 個人情報台帳の整備支援
- 情報漏洩発生時の対応支援
個人情報保護は、継続的な改善が必要です。ぜひ、お困りの際は行政書士にご相談ください。
貴社の個人情報保護体制構築を全力でサポートいたします。
参照情報:
- 個人情報保護委員会:https://www.ppc.go.jp/
- 中小企業向け個人情報保護法ハンドブック(入門編)
- 個人データの漏えい等の事案が発生した場合の対応について https://www.ppc.go.jp/files/pdf/leakage_response.pdf
ご相談・依頼はこちら