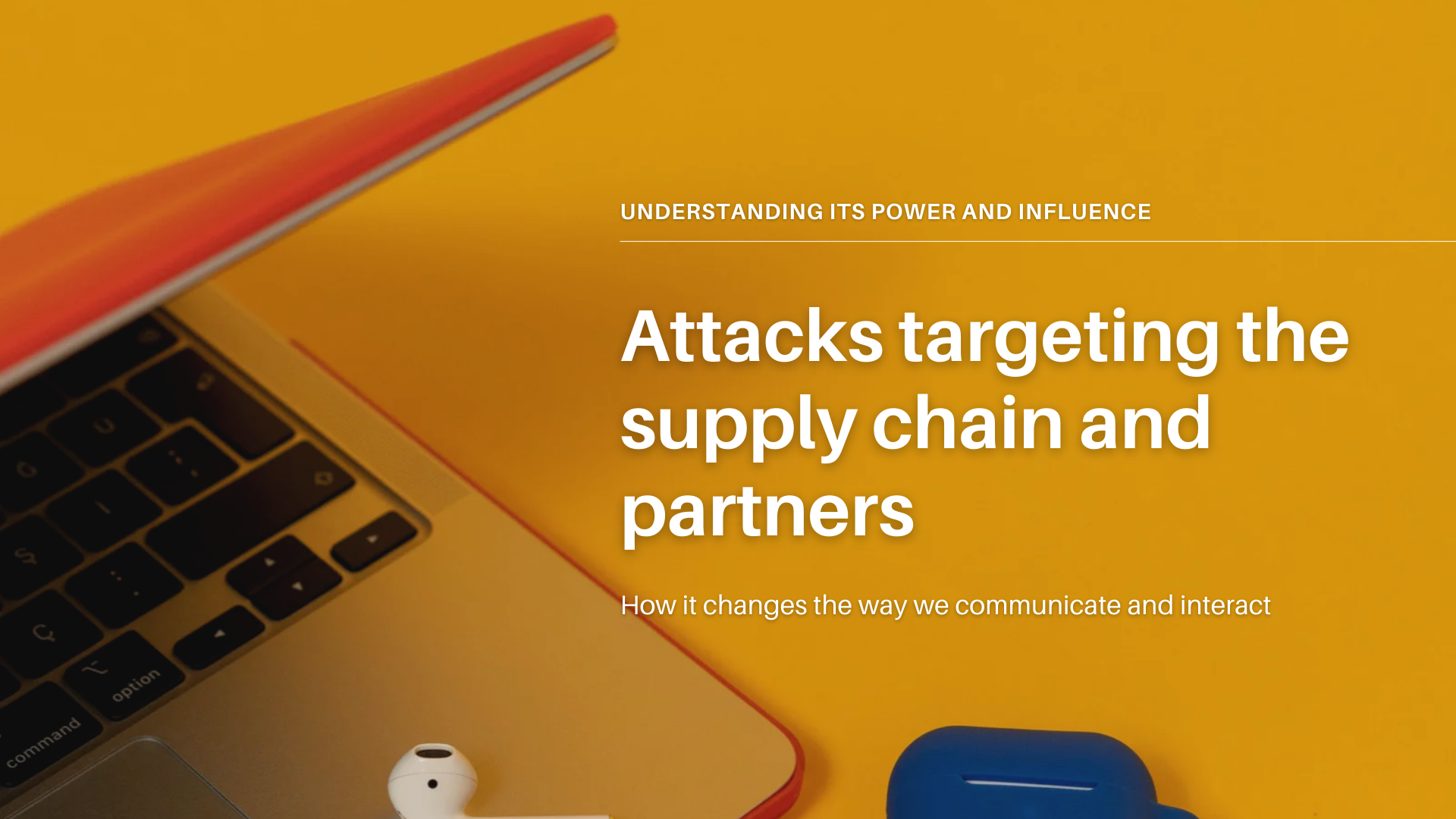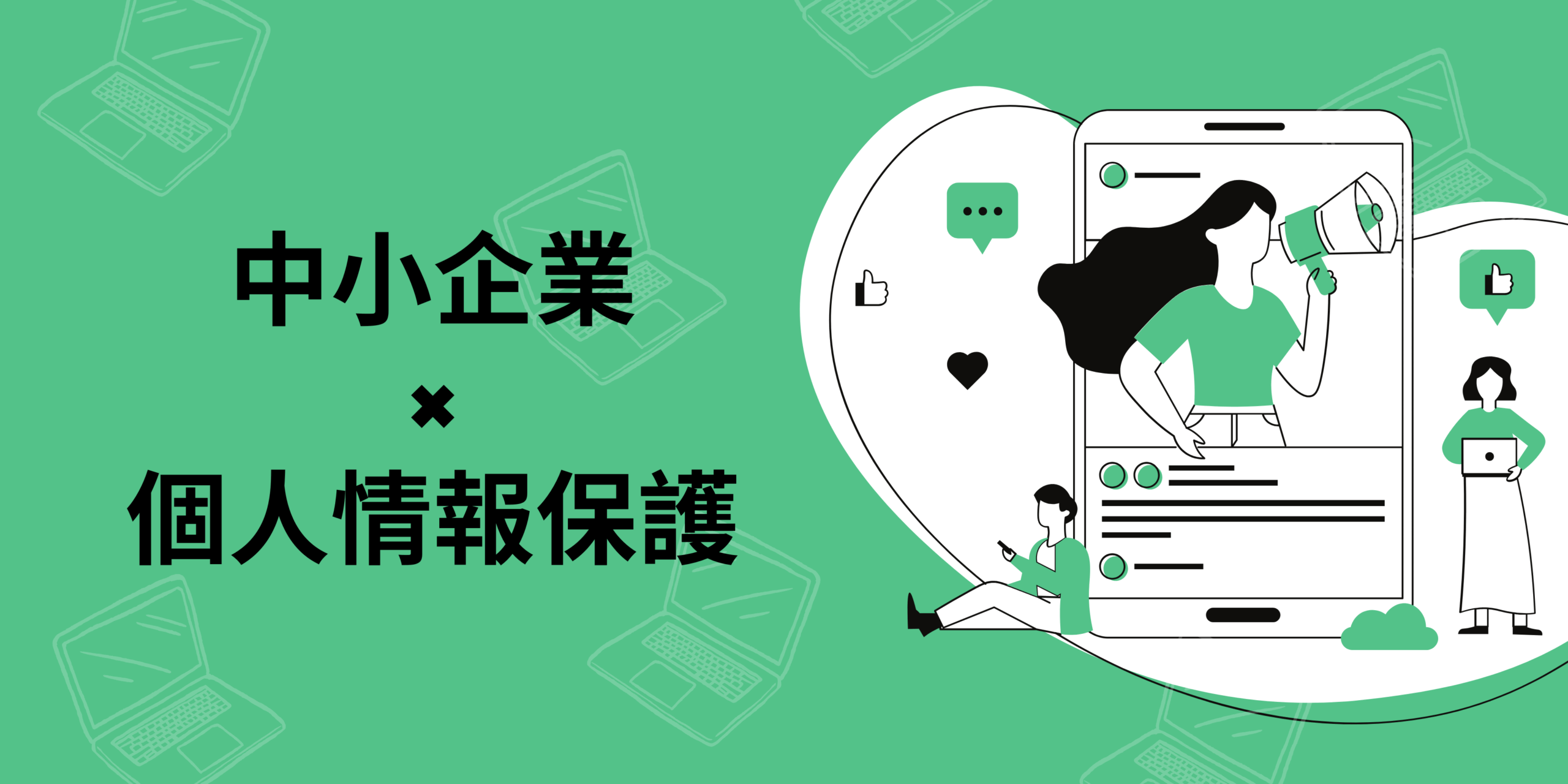中小企業のセキュリティリスク
日々、ニュースなどでは大企業からの情報漏洩、サイバー攻撃による情報の窃取などが取り上げられています。
一方で、多くの経営者の方は、「うちは大企業ではないから、サイバー攻撃の標的にはならないだろう」とお考えかもしれません。
しかし、実際はそうではありません。
IPA(情報処理推進機構)が公表する「情報セキュリティ10大脅威 2025」では、「サプライチェーンや委託先を狙った攻撃」は7年連続でエントリされており、まさに中小企業にとって最大の脅威となりつつあります。
サプライチェーン攻撃とは何か?なぜ中小企業が狙われるのか
サプライチェーン攻撃とは、大企業や政府機関などの主要なターゲットに直接侵入するのではなく、その企業と取引のあるセキュリティ対策が手薄な中小企業を足がかりとして、最終的なターゲットのシステムへ侵入する攻撃手法です。
多くの場合、大企業や政府機関についてはISMSやPマーク取得といった情報セキュリティ対策をしており、攻撃する側としても容易に情報を窃取することはできません。
そこで、「将を射んと欲すれば先ず馬を射よ」とばかりに、中小企業が狙われるのです。
この攻撃が中小企業にとって深刻なのは、以下の理由からです。
- 大企業への「踏み台」にされるリスク
あなたの会社が取引先の大企業にとって、最も脆弱な「入り口」と見なされる可能性があります。
攻撃者は、あなたの会社のシステムに侵入し、そこから大企業のシステムへアクセスしようと試みます。 - 事業停止のリスク
攻撃によってシステムが停止すれば、業務がストップし、事業継続が困難になります。
取引先からの信頼を失い、最悪の場合、事業の閉鎖に追い込まれる可能性も否定できません。 - 損害賠償リスク
情報漏洩が発生した場合、取引先や顧客から損害賠償を請求される可能性があります。
特に個人情報を取り扱っている場合、その責任は重大です。
多くの中小企業が、ITの専門家を社内に置いていません。
また、セキュリティ対策に多額の費用をかけることも難しいでしょう。
しかし、それが攻撃者にとっての「狙い目」となっているのが現状です。
サプライチェーン攻撃の具体的な手口と被害事例
サプライチェーン攻撃の手口は巧妙化しています。
代表的な例として、以下のようなものが挙げられます。
- ソフトウェアの脆弱性を悪用した攻撃
取引先が利用している会計ソフトや顧客管理システムなどのソフトウェアに、悪意のあるプログラムを埋め込むことで、取引先のシステムへ侵入する。 - メールを悪用した攻撃
取引先になりすましたメールを送りつけ、ウイルスに感染したファイルをダウンロードさせたり、偽のウェブサイトへ誘導して認証情報を盗み取る。 - 委託先のシステムへの侵入
データ入力やシステム保守などを外部に委託している場合、その委託先のセキュリティが不十分であれば、そこから情報が漏洩するリスクがあります。
これらの攻撃は、特定の業種や規模に限定されるものではありません。
製造業、サービス業、IT企業など、あらゆる業界の中小企業が標的になりえます。
経営者が知るべき情報セキュリティの基本と法律
情報セキュリティ対策は、もはやIT部門だけの課題ではありません。
企業の存続に関わる、経営者自身が主導すべき重要な経営課題です。
経営者が最低限知っておくべきこと
- サイバーリスクを事業リスクとして認識する
「うちは大丈夫」という楽観的な考えは捨て、サイバー攻撃による事業停止や情報漏洩などのリスクを、火災や自然災害と同様に重要な経営リスクとして認識する必要があります。 - 個人情報保護法改正への対応
2022年の個人情報保護法改正により、中小企業を含むすべての事業者に対して、より厳格な安全管理措置が求められるようになりました。
違反した場合の罰則も強化されています。 - 情報セキュリティ基本方針の策定
どのような情報を守るべきか、誰がどのような責任を負うのかを明確にした、情報セキュリティに関する基本方針を策定し、従業員に周知徹底することが重要です。
中小企業が取り組むべき情報セキュリティ対策の第一歩
いきなり多額の投資をすることは難しいかもしれませんが、まずはできることから始めることが大切です。
- パスワード管理の徹底
簡単なパスワードの使用を禁止し、定期的な変更を促す、二段階認証を導入するなど、パスワード管理のルールを徹底する。 - ソフトウェアのアップデート
OSやアプリケーションの脆弱性を放置しないよう、常に最新の状態にアップデートする。 - 従業員への教育
フィッシングメールの見分け方、不審なサイトにアクセスしないなどの基本的な知識を、定期的な研修を通じて従業員に教育する。
セキュリティインシデントでよくあるのが、「PCが入ったカバンを電車の網棚に忘れてしまった」「飲酒して帰宅したら、会社のスマホがないことに気が付いた」などです。
「情報セキュリティ」というと、高度なIT製品などをイメージするかもしれませんが、アナログな社員教育も同じくらい重要となってきます。
個人情報保護体制の構築|行政書士によるサポート
これまで見てきた通り、個人情報保護法の遵守は企業にとっての法的義務です。
しかし、法律の条文を読み解き、自社に合った体制を構築することは、多くの経営者にとってハードルが高いと感じるかもしれません。
そこで、専門家である行政書士の出番です。
行政書士が支援できること
- 個人情報保護体制の構築支援
個人情報取扱規程や安全管理規程の策定、社内ルールの明確化など、個人情報保護法に準拠した体制を構築するお手伝いをします。 - 特定個人情報(マイナンバー)の安全管理体制構築支援
マイナンバーは、法律で厳格な安全管理措置が定められています。行政書士は、マイナンバーの取得から廃棄までのプロセスを適切に管理するための体制づくりをサポートします。 - 業務委託契約の見直し
外部に業務を委託する場合、委託先が適切な情報セキュリティ対策を講じているかを確認し、契約書にその旨を明記するなど、法的に問題のない契約を締結するお手伝いをします。
個人情報保護は、単なる法的な義務ではなく、顧客や取引先からの信頼を得るための重要な要素です。
適切な体制を構築することで、企業の信用力を高め、事業の安定化に繋がります。
まとめ
個人情報保護の体制構築や情報セキュリティ対策というと、売上に貢献しない「費用」「守り」と認識されがちです。
しかし実際は、しっかりしたPMS(個人情報保護マネジメントシステム)の構築は競合との差別化につながる「投資」であり、情報の取り扱いを通じて、社内の組織風土の改善・ITリテラシーの向上が見込めます。
「何から手をつけていいかわからない」「専門的なことは苦手だ」とお考えの経営者には、まずはミニマムなところからスタートするなど、貴社の状況に合わせた最適な対策をご提案いたします。
お気軽にご相談ください。
ご相談・依頼はこちら